東京都港区に本社を置く化粧品メーカー「ディー・アップ」で、2021年末に発覚したパワーハラスメント問題が注目されています。
2021年4月に新卒入社した女性社員(当時25歳)が社長から激しい叱責を受け、その後うつ病を発症。
休職や自殺未遂を経て2023年10月に亡くなりました。
この事件を受けて2024年5月に労働基準監督署がパワハラと死亡の因果関係を認定し、2025年9月には東京地裁で社長辞任と遺族への1.5億円支払いなどを決める「調停に代わる決定」が出ました。
被害者の痛ましい経緯は企業責任の在り方を問う重要な問題であり、今後の職場環境改善に活かすべき教訓が多く含まれています。
パワハラ行為の詳細
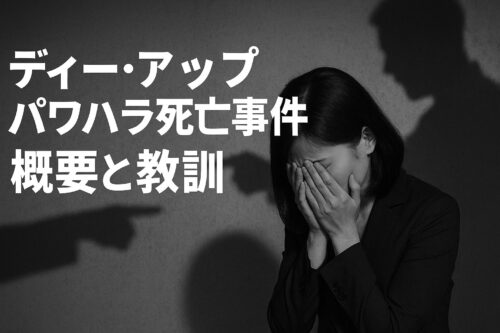
被害者の女性社員は入社当初は期待される人材でしたが、2021年12月に社長との面談を命じられました。
この面談では彼女が許可なく取引先に直行したことが問題視され、社長から50分以上にわたり一方的に厳しい叱責が行われました。
社長は次のような暴言を投げつけたとされます。
- 「お前、大人をなめるなよ」
- 「世の中でいう野良犬っていうんだよ」
- 「力のない犬ほどほえる」
これらの言葉は人格を否定する内容であり、被害者の心に大きな衝撃を与えました。
叱責は翌日にも続き、被害者は精神的に深く追い込まれました。
結果として2022年1月にうつ病と診断されて休職に至り、社内復帰の目途が立たないまま休職期間を迎えました。
会社は休職期間満了を理由に被害者を解雇し、その後被害者は自宅で自殺を図りました。
長時間の療養の末に意識を取り戻すことはなく、2023年10月に亡くなったのです。
- 2021年12月、社長との面談で長時間にわたり一方的に叱責を受けた。
- 2022年1月、うつ病と診断されて休職に入った。
- 休職期間満了を理由に会社が解雇通知を出した。
- 2023年8月、自宅療養中に自殺未遂を図り意識不明となった。
- 2023年10月、意識不明のまま亡くなった。
労災認定と法的判断

被害者死亡後、遺族は社長と会社に責任を追及する訴訟を起こしました。
その中で2024年5月に三田労働基準監督署が調査を行い、社長によるパワハラ行為が被害者のうつ病発症および死亡につながったと因果関係を認定、労災認定を下しました。
つまり「仕事が原因の心身の障害による死亡」として公式に認められたわけです。
さらに2025年9月9日、東京地方裁判所は当事者間の話し合い(調停)に代わる決定を出し、会社側と社長に次の措置を命じました。
- 被害者の遺族に1億5000万円の調停金を支払うこと。
- 事件当時の社長である坂井満氏は辞任すること。
- 会社は社内体制の見直しや再発防止策の実施を約束すること。
これにより遺族と会社は和解が成立し、訴訟は終了しました。
公正な裁判結果により、会社側の責任が法的にも明確になった形です。
会社の対応と再発防止

ディー・アップ株式会社は事件発覚後、社長交代など組織改革を進めています。
公式サイトやプレス発表では、亡くなられた元従業員とご遺族に深くおわびを表明しました。
社内では経営トップが交代したことを公表し、「職場環境の見直しと改善に取り組む」と声明しています。
具体的には、社員からの相談窓口を整備したり、研修や教育を強化したりするなど、働きやすい職場づくりに取り組む方針が示されています。
こうした対応を通じて、再発防止と企業への信頼回復を目指しています。
事件を受け、厚生労働省など国も企業に対策強化を促しています。
パワハラ防止法により、多くの企業には職場での嫌がらせ対策が義務付けられています。
ディー・アップ社の労災認定結果は、企業が定期的な研修やメンタルヘルス支援、内部通報制度の整備などを徹底する必要性を改めて示しました。
今後は経営層自らが率先して職場環境の改善に取り組み、法令遵守と公正な労務管理を徹底することが求められています。
遺族の声・社会の反響
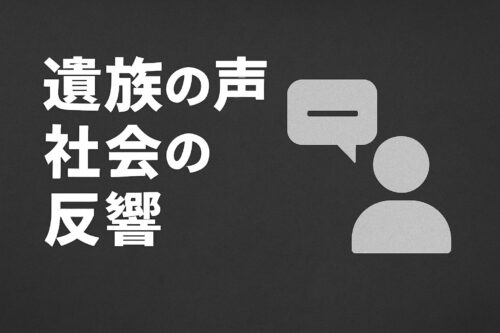
遺族は記者会見で、被害者の人柄と事件への思いを語りました。
被害者の母親は、「娘は全力で人を愛し、いつも周囲を明るくする存在でした。
大切な存在を失った現実が今でも信じられません。若い人たちが安心して働ける職場が増えるよう心から願っています」と述べました。
一方、姉は「妹が亡くなってから何年もたち、今さら謝罪されても気持ちは晴れません。
裁判では結果を得られましたが、生きているうちに謝ってほしかった」と語り、複雑な胸の内を吐露しました。
また、この事件はメディアやSNSでも大きく報じられ、社会に衝撃を与えました。
企業の信頼やブランドイメージが損なわれたことに対し、「パワハラが与える影響は個人だけでなく社会全体に及ぶ」といった声も多く聞かれています。
この事例は、パワハラによる深刻な結果を改めて世間に示すものとなりました。
職場環境改善の重要性
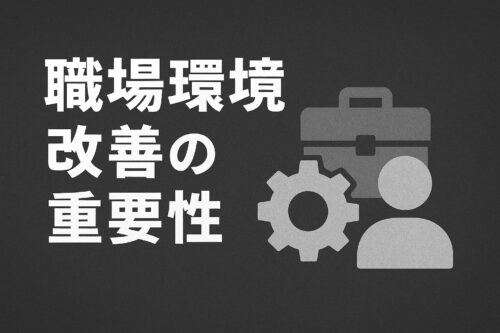
今回の事件は、企業が職場パワハラの防止策を徹底する必要性を浮き彫りにしました。
厚生労働省もパワハラ対策として相談窓口の設置や研修、メンタルヘルスケアの充実を企業の義務と定めています。
企業には研修の実施やストレスチェック体制の強化、ハラスメント相談窓口の周知など、多角的な対策が求められています。
社員が声を上げやすい環境を整えること、経営層が率先してコンプライアンスを徹底することが信頼回復につながります。
従業員側も、パワハラを受けた場合は一人で抱え込まず、社内の相談窓口や労働局、社外の専門家に相談するなど早めの対処が重要です。
万が一職場改善が期待できない状況に追い込まれた場合は、転職や退職も選択肢に入ります。
安全な職場環境を得るためには、自分の身を守る行動も必要です。
退職代行サービスという選択肢
どうしても現在の職場環境から抜け出す必要がある場合、専門の退職代行サービスを利用する手段もあります。
退職代行サービスは、従業員に代わって会社側への退職意思の連絡や各種手続きを代行してくれるサービスです。
上司や人事と直接やり取りする必要がないため、心理的な負担を大幅に軽減できるメリットがあります。
例えば、退職代行サービスでは、専門スタッフが相談から退職手続きまでサポートしてくれます。
自分では伝えにくい状況でも、プロに依頼すれば安心して退職できます。
メンタルヘルスに影響が出る前に、こうしたサービスを活用して安全かつ確実に会社を辞めることも有効な対策の一つです。
職場のパワハラ被害に悩んでいる方は、自分に合った手段で状況を改善することを検討してください。
>実際に退職代行ってどんなサービスがあるの?って思った方はこちらもご覧ください👇
