※本ページはプロモーションが含まれています。
はじめに

近年、退職代行サービスの利用者が急増しています。
かつては「退職は自分で言い出すもの」という考え方が主流でしたが、働き方や職場環境に対する価値観の変化により、「自分一人では辞められない」という悩みを抱える人が増えています。
特に、パワハラや長時間労働、人間関係の悪化などを理由に、精神的に追い詰められている人にとって、退職代行サービスは最後の頼みの綱となることも少なくありません。
厚生労働省の調査によると、20代〜30代の若年層を中心に「退職のハードルが高い」と感じる人が年々増加しています。
その背景には、「辞めると言い出せない」「辞めさせてもらえない」「引き止められるのが怖い」といった、職場特有のプレッシャーや空気感があります。
これらの悩みを解消する手段として、退職代行サービスは一定の支持を集めてきました。
また、SNSや口コミの広がりによって、「実際に退職代行を使ってみた」という体験談も多く見られるようになりました。
利用者の多くが「もっと早く使えばよかった」と感じている一方で、「費用が高い」「トラブルになった」という声もあり、正しい情報をもとに選ぶことが重要です。
本記事では、退職代行サービスの基本的な仕組みから、利用するメリット・デメリット、選び方のポイント、さらには2025年最新のおすすめサービスランキングまで、徹底的に解説していきます。
これから退職代行の利用を考えている方にとって、「読んでよかった」と思える内容をお届けします。
退職代行サービスとは?基本を徹底解説

退職代行サービスとは、利用者が勤務先に対して直接退職の意思を伝えることが困難な場合に、専門業者が本人の代わりに退職の意向を伝えてくれるサービスです。
利用者は退職代行業者と契約を結び、業者が会社との連絡窓口となることで、利用者は一切会社と接触することなく退職の手続きを進めることができます。
このサービスは、特に以下のようなケースで利用されることが多いです。
- 上司に退職を言い出しにくい
- パワハラやセクハラを受けていて直接話したくない
- 引き止めや嫌がらせが予想される
- 会社が退職を受け入れてくれない
- 精神的に限界で話す気力がない
退職代行は単なる連絡代行ではなく、依頼者の安全と精神的安定を守る手段として注目されています。
とくに若年層や、メンタルヘルスの問題を抱える人にとっては、安心して退職できる数少ない方法のひとつです。
2025年現在、退職代行市場はさらに拡大しており、サービスの質も多様化しています。
一部の業者はLINEやチャットによる24時間対応を行っており、スムーズに相談・依頼ができる体制を整えています。
中には転職サポートを兼ねたパッケージを提供している企業もあります。
一方で、退職代行には「非弁行為(弁護士でない者が法律行為を行うこと)」の問題もあります。
退職の意思を伝えること自体は問題ありませんが、未払い給与の請求や有給休暇の交渉といった法律行為を行うには、弁護士資格または労働組合の団体交渉権が必要です。
この点を理解しないまま業者を選んでしまうと、トラブルの原因になりかねません。
退職代行サービスは、単なる逃げの手段ではなく、現代の労働環境が抱える構造的な問題に対する一つの解決策といえます。
自分の人生を守るための正当な手段として、正しく活用することが大切です。
退職代行サービスの3タイプを比較!自分に合うのはどれ?

退職代行サービスはすべて同じように見えるかもしれませんが、実は運営主体によって大きく3つのタイプに分類されます。
それぞれに特徴があり、依頼者の状況や希望に応じて適したタイプを選ぶことが大切です。ここでは、それぞれのタイプについて詳しく解説します。
1. 民間企業運営タイプ
もっとも多く見られるのが、民間企業が運営する退職代行サービスです。
費用の相場は1万円~5万円ほどと比較的リーズナブルで、即日対応や24時間受付など、スピーディーな対応が特徴です。
ただし、注意が必要なのは「交渉権がない」という点です。
法律的な交渉(未払い賃金の請求や有給休暇の取得など)は行えず、あくまで「退職の意思を伝える」だけにとどまります。
これ以上の行為は非弁行為に該当し、違法となる可能性があります。
向いている人:
- 会社との交渉が不要なケース
- 費用を抑えたい人
- まずは静かに退職を伝えたい人
2. 労働組合(ユニオン)運営タイプ
労働組合が運営する退職代行サービスは、憲法28条で保障された「団体交渉権」を活用することで、企業との交渉が合法的に可能です。
費用は2万5,000円〜3万円前後と民間に比べてやや高めですが、交渉が必要なケースでは圧倒的に安心感があります。
例えば、有給休暇の取得や未払い賃金の交渉、離職票の発行依頼などにも対応できるため、「一方的に辞める」だけでなく、正当な権利を主張したい人に向いています。
向いている人:
- 有給や給与などの交渉が必要な人
- トラブルが起きそうな職場にいる人
- 法的に安心な対応を望む人
3. 弁護士運営タイプ
もっとも法的に強力なのが、弁護士が直接運営する退職代行サービスです。
費用は5万円~10万円と高額になりますが、あらゆる法律行為に対応可能です。
未払い賃金の請求、損害賠償への対応、訴訟の代理などもすべて対応範囲に含まれます。
精神的に追い詰められていたり、会社から損害賠償をちらつかされている場合など、トラブルのリスクが高いときは、弁護士に依頼するのが最も安全です。
向いている人:
- 法律トラブルに発展する恐れがある人
- 会社と全面対決の構えで臨む必要がある人
- 確実に法的に有利な形で退職したい人
このように、それぞれの退職代行サービスには明確な違いがあります。
大切なのは、「自分の退職がどの程度のリスクや交渉を含むか」を見極めることです。
単に辞めるだけなのか、法的に守るべき権利があるのか。それによって、最適な選択肢は変わってきます。
利用するメリットとデメリットを正しく理解しよう

退職代行サービスは非常に便利な反面、利用するにあたってはメリットとデメリットを正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、それぞれの観点から詳しく解説していきます。
メリット1:心理的負担を大幅に軽減できる
退職の意思を自分で伝えるのは、精神的に大きなストレスを伴います。
特に、職場の人間関係に悩んでいる場合や、引き止められることが予想される場合は、退職を伝えること自体が大きな壁になります。
退職代行サービスを利用することで、そうした直接的なやり取りを避けることができ、心理的な負担を大きく軽減できます。
メリット2:即日退職が可能なケースもある
民間企業や労働組合が運営する退職代行サービスの中には、即日対応を可能としているところも多くあります。
精神的に限界が来ており、「もう明日から会社に行けない」と感じている人にとって、即日退職という選択肢は大きな救いとなります。
メリット3:手続きを簡略化できる
退職には退職届の提出、会社備品の返却、社会保険や住民税の手続きなど、さまざまなステップが必要です。
退職代行を利用すれば、そうした手続きについても適切なアドバイスを受けながら進めることができるため、不慣れな人でもスムーズに退職できます。
デメリット1:費用がかかる
自分で退職の手続きを行えば基本的に無料ですが、退職代行を使う場合はサービス料金が発生します。
民間企業で1〜5万円、労働組合で2.5〜3万円、弁護士だと5〜10万円と、運営主体によっても費用が大きく異なります。
金銭的に余裕がない場合には負担となる可能性があります。
デメリット2:会社との関係が悪化する可能性がある
退職代行を使うことで、会社側から「筋を通していない」と感じられ、会社との関係が悪化することがあります。
特に、同業種への転職を考えている場合には、前職の評判が新しい職場に伝わるリスクもゼロではありません。
円満退職を重視する人には慎重な判断が求められます。
デメリット3:トラブルのリスクがある
悪質な退職代行業者に依頼してしまうと、退職がスムーズに進まなかったり、会社から直接連絡が来てしまうケースもあります。
また、まれに損害賠償を請求されたり、懲戒解雇として扱われることもあります。
法的知識が不十分な業者を選ぶと、こうしたトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
このように、退職代行サービスは非常に便利で強力な手段である一方、使い方を誤ると大きなリスクも伴います。
利用を検討する際は、自分の状況やリスクをしっかりと分析し、冷静に判断することが何よりも大切です。
退職代行サービスの利用の流れをステップごとに解説

退職代行サービスの利用にあたっては、スムーズな退職を実現するためにも、事前に全体の流れを把握しておくことが重要です。
ここでは、実際に退職代行を使う場合のステップを、時系列に沿って詳しく解説していきます。
ステップ1:退職代行業者に相談する
まずは、複数の退職代行業者に相談を行い、自分に合ったサービスを見極めます。
多くの業者がLINEやメール、電話などで無料相談を受け付けており、サービス内容、料金、対応範囲などを丁寧に説明してくれます。
この時点で、交渉権の有無や即日対応可能かなども確認しておくとよいでしょう。
ステップ2:正式な依頼と料金の支払い
サービス内容に納得できたら、正式に契約を結び、依頼者情報の登録と料金の支払いを行います。
料金体系は業者によって異なり、先払いが一般的ですが、中には「後払い対応」や「全額返金保証制度」を設けているところもあります。
安心して依頼できる業者を選びましょう。
ステップ3:ヒアリングシートに必要事項を記入
退職代行業者から送られるヒアリングシートに、勤務先情報や退職希望日、会社への連絡方法、貸与物の返却方法などの詳細を記入します。
ここでの情報が退職代行の成功を左右するため、正確に記載することが重要です。
ステップ4:退職代行業者が会社に連絡を行う
指定した日に、退職代行業者が会社に連絡し、退職の意思を正式に伝えます。
通常は電話や書面での通知となり、依頼者が会社と直接やり取りする必要はありません。
この時点で、業者が代わりに会社と調整を進め、必要に応じて郵送やLINEでの退職届の提出もサポートしてくれます。
ステップ5:退職届提出・備品の返却・書類の受け取り
退職の意思が伝えられた後は、退職届の郵送や会社支給品(制服、社員証、パソコンなど)の返却、離職票や源泉徴収票などの書類受け取りなど、退職後の手続きが進められます。
多くの代行業者では、これらの手続きの進捗を利用者に随時報告してくれるため、安心して任せることができます。
このように、退職代行サービスの流れは明確であり、計画的に進めればスムーズに退職を完了させることが可能です。
重要なのは、最初の相談段階で「どこまで対応してくれるのか」をしっかり確認すること。そして、対応の丁寧さやレスポンスの速さも業者選びのポイントとなります。
失敗しない退職代行サービスの選び方5つのポイント

退職代行サービスは、人生において大きな転機を迎える重要な場面で利用するものです。
だからこそ、信頼できる業者を選ぶことが何よりも大切です。ここでは、退職代行サービス選びで後悔しないための5つの重要なポイントを紹介します。
1. 運営元を必ず確認する
退職代行サービスには、民間企業、労働組合、弁護士の3つの運営形態があります。
自分の退職が「交渉が必要か」「トラブルに発展しそうか」を見極め、必要な交渉権を持つ運営主体を選ぶことが基本です。
- 単に退職の意思を伝えるだけ → 民間企業でもOK
- 有給取得や未払い給与の交渉が必要 → 労働組合または弁護士に依頼
- 法的トラブルが発生しそう → 弁護士に依頼
交渉権がない業者が法律行為を行うと違法(非弁行為)になるため、慎重な確認が必要です。
2. 実績と口コミをチェックする
実際にサービスを利用した人の声は、非常に信頼できる判断材料です。
公式サイトの実績だけでなく、SNSやGoogleレビュー、掲示板などでの評価も参考にしましょう。
- 「即日で辞められた」
- 「会社と一切やり取りせずに退職できた」
- 「しつこい営業がなかった」
といった評価が多い業者は、安心感があります。
逆に、以下のような口コミが多い業者は注意が必要です。
- 連絡が遅い、返事がない
- 退職後にトラブルが発生した
- 料金と実際のサービス内容が違った
3. 料金とサービス内容のバランスを見る
「安いから」という理由だけで選ぶのは危険です。
料金が安い代わりに、対応が遅かったり、重要な手続きがオプション扱いになっていたりすることもあります。
- 基本料金に含まれている内容は何か
- 有給申請、書類郵送、会社との連絡などはどこまで対応可能か
- 追加料金が発生する条件は明示されているか
これらを確認し、料金とサービスのバランスを冷静に見極めましょう。
4. サポート体制が整っているか確認する
退職は精神的にも不安が多いプロセスです。
だからこそ、サポート体制が充実しているかどうかは非常に重要です。以下の点を確認しましょう。
- 相談は24時間対応か
- LINEやチャットなどで気軽に連絡できるか
- 退職後のフォロー(転職支援や法的相談など)があるか
サポート体制がしっかりしている業者は、利用者の立場を理解し、丁寧に対応してくれます。
5. 「返金保証」や「後払い制度」の有無を確認する
万が一、退職に失敗した場合に備えて、返金保証制度があるかどうかも大事な判断材料です。
特に初めて退職代行を利用する人にとっては、心理的ハードルを下げる安心材料となります。
また、後払い制度がある業者であれば、今すぐ現金の用意が難しい人でも利用しやすくなります。
ただし、後払いは一部の業者に限られるため、事前にしっかり確認しましょう。
退職代行サービスは「どこを選ぶか」で、満足度が大きく変わります。
焦って決めるのではなく、上記の5つのポイントを参考に、自分にとって最適な業者を慎重に選びましょう。
2025年最新おすすめ退職代行サービスランキングTOP5

退職代行サービスは年々数が増えており、どこを選べばよいのか迷う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、実績・信頼性・対応力・価格・サポート体制などを総合的に比較し、2025年最新のおすすめ退職代行サービスをランキング形式でご紹介します。
※ランキングは独自調査と2025年春時点での公開情報をもとに構成しています。
第1位:退職代行SARABA(サラバ)
運営元:労働組合
費用:一律27,000円(税込)
特徴:団体交渉権あり、即日対応、LINE相談OK、追加料金なし
退職代行SARABAは、労働組合が運営しており、法的に正当な交渉力を持っています。
料金は定額制で、追加料金が一切かからないため安心して利用できます。
24時間対応・即日退職にも強く、サポート体制も充実。
迷ったらまず検討したい定番サービスです。
第2位:弁護士法人みやびの退職代行サービス
運営元:弁護士法人
費用:55,000円(税込)~
特徴:法的トラブルに強い、損害賠償請求や未払い賃金請求にも対応
会社との間に法的トラブルのリスクがある場合は、弁護士法人みやびの退職代行が最適です。
有給休暇や残業代請求、損害賠償への対応など、全て合法的に行えるのが最大の強みです。
費用は高めですが、安心感はトップクラスです。
第3位:EXIT(イグジット)
運営元:民間企業
費用:正社員 20,000円、アルバイト 10,000円(税別)
特徴:業界のパイオニア、メディア掲載実績多数、転職支援あり
EXITは退職代行サービスの草分け的存在で、実績と知名度は業界トップクラス。
費用も比較的リーズナブルで、転職エージェントと連携したサポート体制が整っています。
知名度が高いため安心して利用でき、はじめての退職代行にもおすすめです。
第4位:わたしNEXT(女性専用)
運営元:労働組合(女性専用ユニオン)
費用:28,000円(税込)
特徴:女性スタッフが対応、セクハラ・パワハラ問題にも強い、全国対応
女性特有の退職トラブルに対応した「わたしNEXT」は、女性のための退職代行として高い評価を得ています。
相談もすべて女性スタッフが対応するため、安心感が抜群。
職場でハラスメントに苦しんでいる女性にとって、心強い選択肢です。
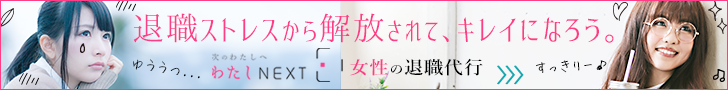
第5位:ニコイチ
運営元:民間企業
費用:27,000円(税込)
特徴:対応が早い、即日対応可能、創業18年の老舗
ニコイチは、退職代行業界でも長い歴史を持つ老舗のサービスです。
スピード対応に定評があり、即日退職にも柔軟に対応可能。
LINEやメールでのサポートも手厚く、丁寧な対応が利用者から高評価を得ています。
各社のサービス比較まとめ
| サービス名 | 運営元 | 費用(税込) | 交渉権 | 即日対応 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| SARABA | 労働組合 | 27,000円 | あり | ○ | 追加料金なし、信頼性高 |
| 弁護士法人みやび | 弁護士 | 55,000円~ | あり | ○ | 法的トラブル対応、安心感あり |
| EXIT | 民間企業 | 20,000円〜 | なし | ○ | 転職支援あり、実績豊富 |
| わたしNEXT | 労働組合 | 28,000円 | あり | ○ | 女性専用、ハラスメント対策に強い |
| ニコイチ | 民間企業 | 27,000円 | なし | ○ | 老舗の安心感、迅速な対応 |
自分の状況や退職に伴うリスクを見極めたうえで、最も適したサービスを選ぶことが、退職成功への近道です。
料金だけでなく、「信頼性」「サポート体制」「交渉力」なども総合的に判断しましょう。
よくある質問Q&Aで不安を解消しよう

退職代行サービスを利用するにあたって、多くの人が疑問や不安を抱えています。
ここでは、よくある質問をQ&A形式でまとめ、ひとつずつ丁寧に解説していきます。
Q1:退職代行サービスは違法ではないのですか?
A:退職代行サービス自体は違法ではありません。退職の意思を本人に代わって伝える行為は合法です。
ただし、民間企業が有給休暇の取得交渉や未払い賃金の請求などを行うと「非弁行為」となり、弁護士法違反に該当する可能性があります。
交渉が必要な場合は、労働組合または弁護士が運営するサービスを利用することが重要です。
Q2:本当に会社に行かずに退職できますか?
A:はい、可能です。退職代行業者があなたの代わりに会社に退職の意思を伝えるため、会社に出向く必要はありません。
制服や社員証などの会社の備品は、郵送で返却するケースがほとんどです。
会社とのやりとりも業者が全て行うため、顔を合わせずに辞めることができます。
Q3:退職代行を使って即日退職できますか?
A:多くの退職代行サービスでは、即日対応が可能です。
特に精神的に追い詰められている場合や、出社が困難な状況では、早期対応が求められます。
ただし、会社側の都合で書類の処理や備品返却に時間がかかることもあるため、実際の「退職完了日」には少し時間を要するケースもあります。
Q4:会社から損害賠償を請求されることはありますか?
A:原則として、退職を理由に損害賠償を請求されることはほとんどありません。
日本の労働法では、労働者は原則2週間前に申し出れば退職が可能です。
ただし、重大なプロジェクトの途中で辞めるなど、特殊な状況下では可能性がゼロではないため、不安がある場合は弁護士が運営する退職代行サービスを利用すると安心です。
Q5:有給休暇は消化できますか?
A:有給休暇の取得は労働者の権利です。
ただし、これを実現するには会社側との交渉が必要となるため、交渉権を持たない民間業者では対応できません。
確実に有給を取得したい場合は、労働組合または弁護士による退職代行サービスを選びましょう。
Q6:退職後に会社から連絡が来たらどうすればいいですか?
A:基本的に会社からの連絡は退職代行業者がブロックしますが、まれに本人宛に連絡が来ることもあります。
その場合は、「すでに代行業者に一任しています」と伝えるだけで問題ありません。
万が一しつこく連絡が来る場合は、業者に報告し、対応を依頼してください。
Q7:再就職に悪影響はありますか?
A:基本的には、退職代行を使ったことが転職活動に直接影響することはありません。
ただし、同じ業界や狭い業界内で転職する場合は、前職の評判が間接的に伝わるリスクはゼロではありません。
気になる場合は、前職との関係が円満に終わるように、労働組合や弁護士の代行を活用して慎重に対応するのがよいでしょう。
このように、退職代行に関する疑問の多くは事前に解消できます。
納得したうえでサービスを利用することで、不安を最小限に抑え、スムーズな退職につなげることができます。
まとめ:退職代行サービスは最終手段ではなく“賢い選択”

退職代行サービスは、もはや一部の人だけが使う「逃げの手段」ではなく、現代社会において必要とされる“賢い選択肢”となっています。
働き方が多様化し、ストレス社会といわれる現代において、退職に悩む人は年々増加しています。
そんな中で、退職代行サービスは、労働者の権利を守り、精神的負担を軽減する有効な手段として注目されています。
退職をめぐるトラブルやストレスから解放されるためには、「自分のために正しく行動する」ことが何よりも大切です。
会社に遠慮して体や心を壊してしまっては、本末転倒です。
退職代行を利用することで、勇気を持って一歩を踏み出すことができたという人は少なくありません。
もちろん、サービスには費用がかかり、選び方を誤ればトラブルに発展する可能性もあります。
しかし、この記事で紹介したように、運営元や交渉力、費用、実績、サポート体制といったポイントをしっかりと確認すれば、自分に合った信頼できる退職代行サービスを見つけることは十分可能です。
大切なのは、「退職すること=悪いこと」という思い込みを手放すことです。
自分の健康と人生を守るためには、時には第三者の力を借りることも必要です。そしてそれは、決して逃げではなく、“前に進むための選択”です。
もし今、「辞めたいのに辞められない」と悩んでいるなら、退職代行サービスはあなたの味方になってくれるかもしれません。
どうか、自分自身の人生を大切にしてください。
>他にも退職代行ってどんなサービスがあるの?って思った方はこちらもご覧ください👇
