1. 2024年発行の新1万円札で初の偽札事件が発生!
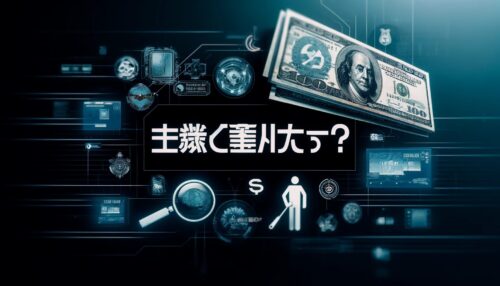
2024年に発行された新1万円札を使用した初の偽札事件が発生しました。
事件が起きたのは東京都新宿区内のコンビニエンスストアで、27歳の男性・斎藤瑞樹容疑者が偽造された新1万円札を使って商品を購入しようとしたことで発覚しました。
全国で初めての新紙幣の偽札事件として注目されており、警察はこの事件をきっかけに、今後の偽札対策を強化する方針を示しています。
事件の概要
- 発生場所:東京都新宿区のコンビニ
- 逮捕者:27歳の斎藤瑞樹容疑者(台東区在住)
- 使用された偽札:2024年発行の新1万円札
- 偽札の特徴:ホログラムが不自然、透かしがない
事件の発覚により、警視庁は斎藤容疑者の自宅を家宅捜索し、50枚以上の偽札を押収しました。
偽札は自宅のプリンターで作成されたとみられ、その精度は低かったことが判明しています。
次の章では、偽札事件がどのように発覚したのかを詳しく見ていきます。
2. 偽札事件の発覚と通報の経緯
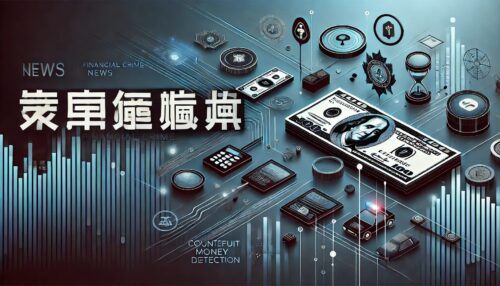
この偽札事件は、新宿区のコンビニエンスストアで発覚しました。
斎藤瑞樹容疑者が偽造された新1万円札を使って商品を購入しようとした際、店員が紙幣の異常に気づき、警察に通報したことで事件が明るみに出ました。
店員が不審に思ったポイント
店員は、以下の点に違和感を抱きました。
- ホログラムの光り方がおかしい
- 本物の新1万円札は、角度を変えると3D効果で渋沢栄一の肖像が浮かび上がる。
- しかし、偽札はホログラムの変化がなく、不自然な光り方だった。
- 透かしの肖像が見えない
- 新紙幣には、光に透かすと肖像が浮かび上がる透かし技術が使われている。
- しかし、偽札は普通の紙に印刷されたもので、透かしが存在しなかった。
- 紙の質感が違う
- 本物の紙幣は特殊な素材で作られており、手触りが独特。
- 偽札は普通のコピー用紙のような質感で、違和感があった。
通報から事件発覚までの流れ
- 店員が偽札の異常に気づき、警察に通報
- 警察官が駆けつけ、その場で斎藤容疑者を取り押さえる
- 持っていた紙幣を確認し、偽札と判断
- 斎藤容疑者をその場で逮捕
さらに、警察が斎藤容疑者の自宅を家宅捜索したところ、50枚以上の偽札が見つかりました。
偽札は、自宅のプリンターで印刷されたものとみられ、精度が低かったため、簡単に見破られたのです。
では、斎藤容疑者はどのようにして偽札を作成し、それがどのように発覚したのでしょうか?
次の章で詳しく解説します。
3. 逮捕の経緯と押収された偽札
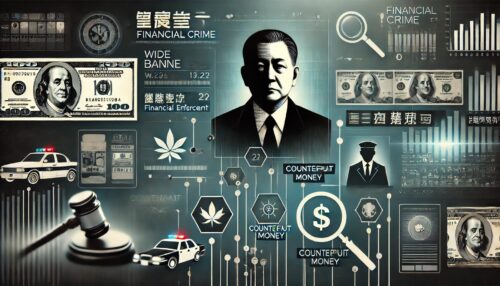
警察の捜査により、斎藤瑞樹容疑者が自宅のプリンターを使って偽札を作成していたことが明らかになりました。
発覚のきっかけは、新宿区のコンビニ店員が偽札の異常に気づき、警察に通報したことでした。
警察が現場に駆けつけ、その場で斎藤容疑者を取り押さえたことで事件は一気に展開しました。
逮捕の流れ
- 店員の通報を受けた警察官が現場へ急行
- 斎藤容疑者の持っていた紙幣を確認し、偽札と判明
- 斎藤容疑者をその場で逮捕
- 自宅を家宅捜索し、50枚以上の偽札を押収
押収された偽札の特徴
警察が斎藤容疑者の台東区の自宅を家宅捜索したところ、以下のような証拠が発見されました。
- 新1万円札と5000円札の偽札50枚以上
- 偽札を印刷するために使用したプリンター
- 紙幣のデザインを編集するためのパソコンとソフトウェア
今回の事件で押収された偽札は、家庭用プリンターで作成されたものであり、その精度は極めて低かったと警察は発表しています。
なぜ偽札は簡単に見破られたのか?
斎藤容疑者が作成した偽札は、本物の紙幣と比較して以下の点が明らかに異なっていました。
- ホログラムが印刷されたものだった
- 本物の新1万円札は、角度を変えると肖像が3Dで浮かび上がるホログラム技術が使用されている。
- しかし、偽札はホログラム部分を単に印刷しただけで、立体的な変化がなかった。
- 透かし技術がなかった
- 本物の紙幣は、光に透かすと肖像が浮かび上がる。
- 偽札は普通のコピー用紙を使用していたため、透かしがなく一目で偽物と分かった。
- 紙の手触りが異なる
- 本物の紙幣は、特殊な素材を使っており、手触りが独特。
- 偽札は家庭用の紙を使用しており、質感がまったく異なっていた。
さらに、斎藤容疑者は偽札を使った後もその場に留まっていたことが、逮捕に至る決定的な要因となりました。
一般的に偽札を使用する犯罪者は、発覚を恐れてすぐに現場を離れる傾向があります。
しかし、斎藤容疑者は逃げることなく店内にとどまっていたため、店員が通報しやすい状況だったのです。
次の章では、偽札を見破るためのチェックポイントを詳しく解説します。
4. 偽札を見破るためのポイント

今回の偽札事件では、コンビニ店員が偽札の異常に気づいたことが早期逮捕につながりました。
偽札は巧妙に作られることが多いため、一般の人でも偽物と本物を見分けられるようにすることが重要です。
ここでは、新1万円札の特徴を活かした偽札の見破り方を解説します。
1. ホログラムの確認
新1万円札の最大の特徴の一つは、3Dホログラムです。
✅ ホログラムの見え方をチェック
- 本物の紙幣では、角度を変えると渋沢栄一の肖像が3Dで浮かび上がる。
- 偽札では、単なる印刷で再現しているため、角度を変えても変化がない。
今回の事件でも、ホログラムの不自然さが偽札発覚の決め手になりました。
2. 透かしを確認
✅ 紙幣を光に透かして見る
- 本物の新1万円札には、透かし技術が施されており、光にかざすと肖像が浮かび上がる。
- 偽札は通常の紙に印刷されているため、透かしが存在しない。
これは簡単にチェックできるポイントなので、疑わしい紙幣は必ず光に透かして確認しましょう。
3. 紙の質感と印刷技術をチェック
✅ 指で触って感触を確かめる
- 本物の紙幣は、特殊な素材(和紙)を使用しており、独特のざらつきがある。
- 偽札は普通のコピー用紙やインクジェット用紙に印刷されるため、滑らかで違和感がある。
また、本物の紙幣は、「深凹版印刷(しんおうはんいんさつ)」という特殊な技術が使われており、数字や肖像の部分がわずかに盛り上がっています。
これを指でなぞると、本物は立体感があるのに対し、偽札はただの平面印刷であるため、感触の違いが分かります。
4. マイクロ文字や隠し文字を確認
✅ 紙幣をよく見ると、小さな文字や模様が確認できる
- 本物の紙幣には、**「NIPPON」「10000」などの微細な文字(マイクロ文字)**が印刷されている。
- 偽札では、家庭用プリンターでは細かい文字の再現が難しく、文字がつぶれていることが多い。
また、新1万円札には「潜像文字(せんぞうもじ)」が採用されており、斜めの角度から見ると「10000」の数字が浮かび上がる仕組みになっています。
偽札では、この技術を再現できないため、簡単に見破ることができます。
5. ブラックライトを当ててチェック
✅ 紫外線を当てると本物は特定の部分が光る
- 本物の紙幣は、ブラックライト(紫外線)を当てると特定の部分が光るように設計されている。
- 偽札は一般のプリンターで作られるため、光に反応しない。
コンビニや金融機関では、紙幣の真偽を確認するためにブラックライトを使うことが増えています。
家庭でも安価なブラックライトを購入して、簡単にチェックすることができます。
まとめ:偽札を見破るチェックリスト
✅ ホログラムを確認(角度を変えて3D変化があるか?)
✅ 光に透かして肖像が見えるか?
✅ 紙の質感がざらついているか?(コピー用紙のようなツルツルした質感はNG)
✅ マイクロ文字や隠し文字が正しく印刷されているか?
✅ ブラックライトを当てて光る部分があるか?
これらのポイントを押さえておけば、偽札を見破ることが可能です。
次の章では、今回の事件が今後の偽札対策にどのような影響を与えるのかについて解説します。
5. 今後の偽札対策と影響
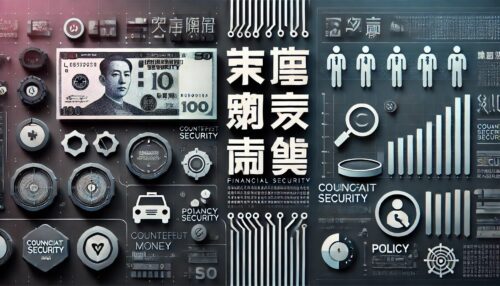
今回の偽札事件は2024年に発行された新1万円札で初めて発生したものであり、全国的に大きな注目を集めました。
この事件を受け、金融機関や店舗、消費者の間で偽札対策の強化が求められています。
今後、どのような影響があるのかを詳しく見ていきましょう。
1. 金融機関や店舗での偽札対策の強化
銀行やコンビニ、スーパーなど、現金を扱う店舗では、今回の事件を受けて紙幣の真贋確認を徹底する動きが強まると考えられます。
✅ 導入が進むと考えられる対策
- レジでの紙幣チェックを強化(特にホログラムや透かしの確認)
- 偽札検出機(ブラックライトや紫外線検知装置)の設置を拡大
- 店員向けの研修を実施し、偽札の見分け方を教育
特にコンビニなどの店舗では、レジ係の意識向上が重要です。
今回の事件でも、店員が紙幣の異常に気づき、すぐに警察に通報したことで事件が早期解決につながりました。
2. 新紙幣の偽造防止技術のさらなる向上
日本の紙幣には高度な偽造防止技術が施されていますが、今回の事件を受けて、さらに強化される可能性があります。
✅ 考えられる技術の強化
- ホログラム技術のさらなる進化(3D効果をより複雑化)
- 新たなセキュリティインクの導入(紫外線や特定の光でしか見えない印刷)
- QRコードやデジタル識別技術の追加
すでに海外では、紙幣にスマートチップやデジタル認証を組み込む技術が開発されており、日本でも導入が検討される可能性があります。
3. 偽札犯罪への厳罰化と取り締まりの強化
日本では偽札の製造や使用は「通貨偽造罪」に該当し、無期懲役または3年以上の懲役刑が科されます。
今回の事件を受けて、警察は偽札犯罪の取り締まりをさらに強化する方針を示しています。
✅ 今後の取り締まり強化のポイント
- 偽札に関する通報体制を強化(警察への迅速な報告ルートの確立)
- インターネット上の違法な偽札販売サイトの監視強化
- 金融機関や店舗と連携し、偽札使用の早期発見を徹底
特に、最近では偽札データの販売や紙幣デザインの違法ダウンロードが増えており、警察はこれらの動きを監視する体制を強化しています。
4. 消費者が注意すべきポイント
今回の事件は、新紙幣発行後の早い段階で発生しました。
今後も偽札事件が増える可能性があるため、消費者自身も紙幣の真贋を確認する意識を持つことが重要です。
✅ 消費者ができる対策
- 現金での取引時に紙幣のホログラムや透かしをチェックする
- 高額紙幣の受け取り時は特に慎重に確認する
- 怪しい紙幣を見つけたらすぐに店舗スタッフや警察に報告する
また、キャッシュレス決済が普及しているとはいえ、現金取引はまだ多くの場面で必要になります。
消費者自身が正しい知識を持ち、偽札を見抜く力を養うことが求められます。
まとめ
今回の偽札事件は、全国的に大きな波紋を広げました。
この事件を受け、今後は以下のような対策が進められることが予想されます。
✅ 金融機関や店舗での偽札チェック強化(レジでの確認、偽札検知機の導入)
✅ 紙幣の偽造防止技術のさらなる向上(ホログラム技術の強化、新たな識別技術の導入)
✅ 偽札犯罪の取り締まり強化(警察の監視体制強化、偽札販売サイトの摘発)
✅ 消費者の意識向上(紙幣の確認方法を学び、怪しい紙幣を見つけたら通報)
新しい紙幣が発行されるたびに、偽札犯罪も進化していきます。
今後、金融機関や店舗、消費者が連携し、偽札犯罪を未然に防ぐことが重要となるでしょう。