はじめに ― 「ちゃん付け」が論点となった背景

2025年10月、東京地裁が下した判決が日本中に衝撃を与えました。
それは「職場での“ちゃん付け”がハラスメントにあたる」と認定された、前例の少ない判決です。
事件の舞台は、大手物流会社の営業所。40代の女性社員が、同僚の男性から日常的に「○○ちゃん」と呼ばれ続け、加えて「かわいいね」「体型が変わったね」などといった発言を受けていました。
被害を受けた女性は、これらの言動によって強い羞恥心と不快感を覚え、働く環境が著しく悪化したとして訴えを起こしました。
裁判所は、この一連の呼称や発言を「許容される限度を超えた違法なハラスメント」と判断。
男性に対して22万円の慰謝料支払いを命じる判決を下しました。
この判決が注目された理由は、単にセクハラを認定したからではありません。
多くの職場で「親しみを込めた呼び方」として行われていた“ちゃん付け”が、受け手の感じ方によっては違法と判断される時代になったという点にあります。
ここで問われるのは、言葉そのものではなく、「相手がどう感じたか」という観点です。
どれほど軽い気持ちの発言であっても、相手が不快に感じればそれはハラスメントに該当します。
時代は今、「悪意がないから大丈夫」という認識から、「受け手がどう感じるかを尊重する」方向へと大きく変わりつつあるのです。
職場の呼び方やコミュニケーションは、長年の慣習に基づいて行われてきました。
しかし、この判決はその“常識”を根本から問い直す転機となりました。
この記事では、この事例をもとに以下の内容を解説していきます。
- なぜ“ちゃん付け”がハラスメントと認定されたのか
- セクハラとパワハラの境界線
- 呼び方に潜むリスクと職場での注意点
- 呼ばれた側・呼ぶ側がそれぞれ取るべき対応
- 今後の企業が取るべき防止策
“呼び方ひとつで人を傷つけない職場”をつくるために、
まずはこの判決が投げかけたメッセージを正しく理解することが大切です。
第二章 ― 最新判決の内容 ― どんな言動が法律的に問題とされたか
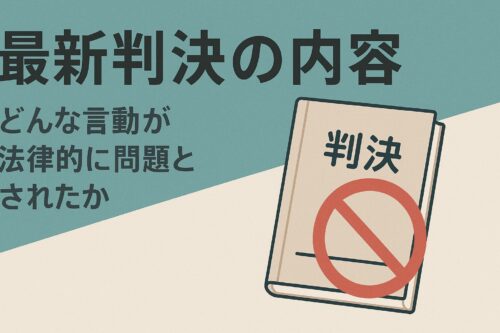
今回の東京地裁の判決は、ハラスメントをめぐる日本の労働環境において新たな基準を示す画期的なものとなりました。
裁判では、被告となった男性の言動が「職場における適切な人間関係の範囲を逸脱していたか」が焦点となりました。
判決で認定された具体的な行為
裁判所が「違法なハラスメント」として認定した行為は、次の3点です。
- 2020年以降、継続的に“ちゃん付け”で呼び続けたこと
- 容姿や体型についての発言(例:「かわいいね」「太った?」など)
- 業務に関係のないプライベートな会話を繰り返したこと
これらの行為は、当人同士の関係性や会話の内容から見ても「親しみを込めたもの」とは言えず、むしろ被害者の羞恥心や尊厳を傷つける性質があると判断されました。
裁判所の判断のポイント
田原慎士裁判官は、判決文の中で次のように指摘しています。
「女性の羞恥心を害する内容であり、職場における環境型セクシュアルハラスメントに該当する」
この“環境型セクハラ”とは、直接的な身体的接触や明確な性的要求がなくても、
性的な言動によって職場環境を不快にし、就労に悪影響を与える行為を指します。
つまり、被害者が「職場で過ごしにくい」「仕事に集中できない」と感じるような状況を作り出した時点で、ハラスメントとして成立する可能性があるということです。
慣習や悪意の有無は“免罪符”にならない
被告男性は、「昔から“ちゃん付け”で呼んでいた」「悪意はなかった」と主張しました。
しかし、裁判所はこの主張を退けています。
理由は明確で、ハラスメントの成立要件は“加害者の意図”ではなく“被害者の受け止め方”に基づくためです。
過去には許容されていた慣習的な行為でも、社会の価値観や職場文化が変化すれば、
同じ行為が違法と判断されることがあります。
今回の判決はその典型的な例です。
慰謝料22万円という金額の意味
慰謝料22万円という金額は、数字だけを見れば高額とは言えません。
しかし、法的には「社会的制裁を伴う違法行為として認定された」ことが重要です。
つまりこの判決は、「たかが呼び方」という感覚を否定し、
“言葉の使い方”にも法的責任が伴うことを明確に示したといえます。
判決が企業や社会に与えるインパクト
この判決をきっかけに、企業は以下の点で対応を迫られることになります。
- 呼称・コミュニケーションに関するガイドラインの見直し
- ハラスメント防止研修の強化
- 社内相談体制の整備
今後は「悪意がなかった」「慣れていた」という弁解は通用せず、
“無自覚なハラスメント”も防止する組織文化づくりが求められていきます。
第三章 ― なぜ「ちゃん付け」がセクシュアル・ハラスメントになるのか

「ちゃん付け」や「くん付け」といった呼び方は、これまで多くの職場で“親しみ”や“フランクさ”を表す言葉として使われてきました。
しかし近年、職場での人間関係や価値観の変化により、それがハラスメントとして問題視されるケースが増えています。
セクシュアル・ハラスメントの基本構造
セクシュアル・ハラスメント(以下、セクハラ)は、職場での性的な言動により、他者に不快感や屈辱感を与える行為を指します。
厚生労働省の指針では、セクハラは大きく以下の2種類に分類されています。
- 対価型セクハラ
昇進や評価などの見返りを条件に、性的な言動を強要するタイプ。
例:「飲み会で一緒に座らないと評価を下げるぞ」といった発言。 - 環境型セクハラ
性的な発言や態度によって職場の環境を不快にし、働く意欲を損なうタイプ。
今回の“ちゃん付け”判決は、この「環境型セクハラ」に該当します。
つまり、直接的な要求や接触がなくても、相手が不快に感じた時点でハラスメントが成立するのです。
「ちゃん付け」が問題視される理由
一見、無害に思える「ちゃん付け」がハラスメントとされる背景には、次の3つの要因があります。
① 上下関係の中での“支配構造”
職場では、年齢・立場・性別によって力のバランスが存在します。
上司や年上の男性からの「○○ちゃん」という呼称は、無意識のうちに上下関係を強調し、相手を軽んじている印象を与えることがあります。
被害者が「子ども扱いされている」「対等に扱われていない」と感じた場合、それだけで職場環境は不快になります。
② 性的ニュアンスが含まれる可能性
「ちゃん付け」には、親密さやかわいらしさを強調するニュアンスがあります。
そのため、特に異性間では恋愛的・性的な意図を含むものとして受け取られやすいのが現実です。
本人に悪気がなくても、相手が「性的に見られている」と感じた瞬間に、セクハラの要件を満たす可能性があります。
③ 社会的価値観の変化
かつては「フランクな関係」「親しみを込めた呼び方」として許容されていた行為も、
現代では「個人の尊厳を損なう行為」として見直されています。
とくにZ世代を中心に、「距離の近さよりも相互のリスペクトを重視する文化」が広がっており、
“呼び方”に対する感覚も大きく変化しているのです。
「本人が嫌と言っていない」は通用しない
多くの加害者が誤解しているのが、「相手が明確に嫌と言っていないから大丈夫」という認識です。
しかし現実には、職場の上下関係や雰囲気から「言いづらい」「波風を立てたくない」と感じ、沈黙を選ぶ人が圧倒的に多いのです。
沈黙は同意ではなく、むしろ「耐えている」ことを意味するケースも少なくありません。
ハラスメントの成立は“意図”ではなく“影響”
ハラスメントの判断において最も重要なのは、加害者の意図ではなく被害者への影響です。
つまり、「悪意があったかどうか」ではなく、
その言動が結果として相手の尊厳や働く意欲を損なったかどうかが問われます。
“ちゃん付け”という一言でも、相手が「不快」「屈辱的」と感じたなら、
それは立派なセクシュアル・ハラスメントと認定され得るのです。
第四章 ― 呼称以外にも注意すべき“危険な呼び方”

「ちゃん付け」だけでなく、職場では他にも無意識のうちに相手を傷つけてしまう呼び方が数多く存在します。
その多くは“昔からの慣習”や“軽い冗談”として使われていますが、現代の価値観ではハラスメントに該当するおそれがあります。
ここでは、実際の職場で問題になりやすい呼称と、その理由を具体的に整理します。
呼び方ひとつで印象が180度変わる
呼称は人間関係を築くうえで欠かせない要素ですが、同時に相手の尊厳や心理的安全性に直結します。
同じ言葉でも「誰が・どんな場面で・どんな口調で使うか」によって、受け取られ方は大きく変わります。
問題になりやすい呼び方とその理由
| 呼び方 | 問題点・感じやすい不快感 |
|---|---|
| 「お前」 | 命令口調・支配的態度と受け取られやすく、パワハラ要素を含む |
| 呼び捨て | 敬意を欠く表現で、上下関係を誇示していると感じる人も多い |
| 「女の子」「男の子」 | 大人を子ども扱いする表現であり、ジェンダー的な差別感を助長 |
| 「くん付け」 | 性別によって使い分けると不公平感を生みやすく、性差別と捉えられる場合がある |
| あだ名・ニックネーム | 本人が嫌がる呼称であれば、いじめ・モラハラの要素を含む |
| 外見をもじった呼び方(例:「ぽっちゃり」「天然」) | 身体的特徴や性格を揶揄する表現は、人格否定につながる |
これらは一見すると冗談や愛称のように見えても、相手が不快に感じれば立派なハラスメントです。
特に職場では、冗談であっても「権力関係」「業務上の指示」と結びつくため、受け手に与える影響は非常に大きくなります。
性別による呼称の偏りにも注意
日本企業では、いまだに「女性社員=○○ちゃん」「男性社員=○○くん」という慣習が根強く残っています。
しかしこのような使い分けは、性別による差別的扱い(ジェンダーハラスメント)と見なされるリスクがあります。
たとえば同じ部署で女性だけが「ちゃん付け」、男性だけが「さん付け」されている場合、
「女性を軽く扱っている」「対等に見ていない」と感じる人が出ても不思議ではありません。
ジェンダーに基づく呼称の違いは、本人の意図を超えて組織全体の信用を損なう要因にもなります。
「悪気がなかった」では済まされない時代へ
かつては「軽口」「冗談」で片付けられていた言葉も、現代では法的・倫理的責任を問われる時代です。
SNSなどでの発言が外部に拡散すれば、企業イメージや信頼の失墜にも直結します。
「言葉は軽くても、影響は重い」。
この意識を、すべての働く人が持つことが求められています。
敬意ある呼称を選ぶのが基本
安全でトラブルを避ける呼び方の基本は、以下の通りです。
✅ 「さん付け」を徹底する
✅ 役職名(例:課長・部長・先生など)を使う
✅ 個人名を避けたい場合は「○○担当」「○○チームの方」など業務ベースで呼ぶ
これらを意識するだけで、職場の空気は驚くほど穏やかになります。
呼称は人間関係の“入口”であり、最初の一言でその人の尊敬度が測られてしまうのです。
第五章 ― 呼ばれる側が取るべき対応と、呼ぶ側が気を付けるべきこと
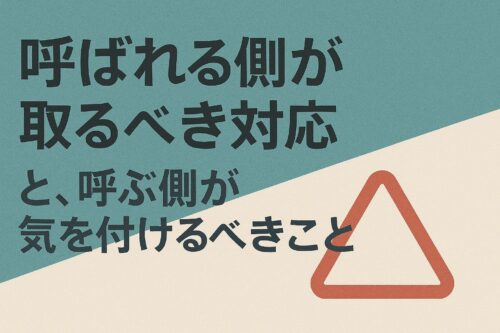
ハラスメント問題の多くは、「言い出せなかった」「悪気があるとは思えなかった」という小さなすれ違いから始まります。
しかし、違和感を放置すると心の負担が蓄積し、やがて職場全体の信頼関係が崩れることにつながります。
この章では、呼ばれる側と呼ぶ側の双方が意識すべきポイントを整理します。
呼ばれる側が取るべき3つのステップ
① 早めに違和感を伝える
最も大切なのは、「嫌だ」と思った段階で早めに意思を示すことです。
遠回しでも構いません。
たとえば次のように伝えることで、相手に不快感を伝えることができます。
- 「○○さんと呼んでもらえると助かります」
- 「仕事の話は“さん付け”でお願いできますか?」
“指摘”ではなく“提案”として伝えると、相手も受け入れやすくなります。
曖昧なままにしておくと、相手は「嫌がっていない」と誤解して行為を続けてしまうため、早めの対応が重要です。
② 明確に伝えても改善されない場合は相談を
勇気を出して伝えても状況が変わらない場合は、第三者機関への相談を検討しましょう。
多くの企業には以下のような窓口があります。
- 人事部やコンプライアンス部門
- 社内ハラスメント相談窓口
- 労働局や労働基準監督署の相談センター
記録を残すために、メールや日付入りメモなどの形でやり取りを保存しておくことも大切です。
証拠があることで、万が一訴訟や調査に発展した場合にも自分を守ることができます。
③ 自分を責めない
「相手を傷つけたくない」「自分が神経質なのかも」と悩む人も少なくありません。
しかし、不快と感じたあなたの感覚は正当です。
ハラスメントの判断基準は“相手がどう感じたか”であり、感じ方に優劣はありません。
「我慢すれば丸く収まる」と思わず、心の安全を最優先に行動しましょう。
呼ぶ側が気を付けるべきポイント
呼称に関するトラブルの多くは、「親しみを込めたつもりだった」「場を和ませたかった」という善意から起こります。
しかし、現代では善意でもハラスメントになることを理解する必要があります。
① 呼び方は“さん付け”が基本
職場での呼称は「○○さん」または役職名が最も安全です。
たとえ同僚や後輩であっても、立場の違いがある場では“さん付け”を徹底するのが社会的マナーです。
一貫性を持たせることも大切です。
特定の人だけ“ちゃん付け”や呼び捨てにすると、差別的扱いと見なされるおそれがあります。
② 「自分は大丈夫」は通用しない
「自分はハラスメントをするようなタイプじゃない」と考える人ほど、
無意識のうちに相手を不快にさせているケースが多く見られます。
“慣れ”や“フランクさ”は紙一重。
相手の反応をよく観察し、少しでも違和感を感じたら即座にやめる姿勢が求められます。
③ 過去の常識にとらわれない
「昔は普通だった」「職場の雰囲気を壊したくない」という理由で時代に逆らうことは、
結果的に自分や企業のリスクを高める行為です。
社会の価値観は変化しています。
“言葉のアップデート”は、もはや個人の努力ではなくビジネスマナーの一部なのです。
両者に共通する意識 ― “敬意”と“距離感”
最終的に、ハラスメント防止の根底にあるのは敬意と適切な距離感です。
呼び方は単なる言葉ではなく、「あなたをどう扱っているか」というメッセージそのもの。
相手を尊重する呼び方を選ぶことが、信頼と安心の職場をつくる第一歩です。
第六章 ― 企業・職場で進めるべきハラスメント防止のためのガイドライン
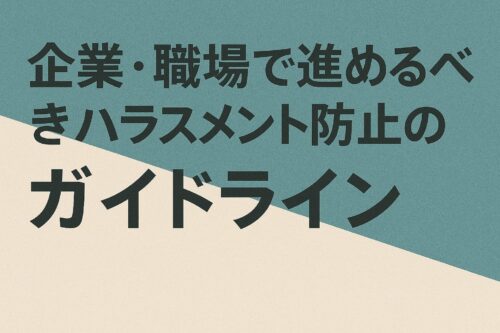
「ちゃん付け」判決が示したのは、個人の問題にとどまらず、企業文化全体のアップデートが求められているという現実です。
これからの時代、企業が「ハラスメントを起こさない」だけでなく、「起こりにくい職場を仕組みとしてつくる」ことが重要になります。
ここでは、企業・管理職・同僚それぞれが取るべき実践的な対策を整理します。
ステップ① 明文化された「ハラスメント防止方針」を策定する
最初の一歩は、会社としてハラスメント防止方針を明文化することです。
曖昧なまま「常識で判断」してしまうと、個人の感覚の違いによってトラブルが発生します。
具体的には以下のような文書化が有効です。
- セクハラ・パワハラ・モラハラなど各種ハラスメントの定義
- 不適切な言動・呼称・コミュニケーションの具体例
- 社員・上司・経営層の責任範囲と行動指針
- 通報・相談を行った社員を保護する仕組み
これらを社内ポータルや掲示などで共有し、誰もがアクセスできる状態にしておくことが大切です。
また、新入社員研修や昇進時研修などで繰り返し説明することで、組織全体の意識が定着していきます。
ステップ② 相談・通報の「安心ルート」を確保する
多くの被害は「相談しづらい雰囲気」や「報復への恐れ」から放置されています。
企業は、安心して声を上げられる環境づくりを優先しなければなりません。
有効な仕組みとして、次のようなものがあります。
- 匿名で相談できる内部通報窓口の設置
- 第三者機関(社外弁護士や社労士)との連携窓口
- ハラスメント担当者を男女・複数人配置
- 報復行為を禁止する社内規程の明示
相談を受けた担当者には、守秘義務・迅速な対応・被害者保護の徹底を義務付けることが欠かせません。
ステップ③ 管理職への教育を徹底する
ハラスメント防止において、最も重要な役割を担うのが管理職です。
上司の一言が職場全体の空気を左右するからです。
管理職研修では、次の内容を重点的に取り上げると効果的です。
- ハラスメントの法的責任とリスク(懲戒・損害賠償など)
- 言葉遣いや呼称が与える心理的影響
- 部下からの相談を受けた際の対応フロー
- 自分が「加害者・黙認者」にならないための意識づけ
単なる座学で終わらせず、ロールプレイ形式で「不快な呼び方」「無意識の差別」を体験させる研修が、行動変化に直結します。
ステップ④ 定期的なアンケートとフィードバック制度
年に1回の社内アンケートでハラスメントの有無を調査する企業も増えています。
このとき重要なのは、匿名性の確保と行動への反映です。
「意見を出しても何も変わらない」と感じる職場では、声は上がりません。
アンケート後には以下のような対応を取るとよいでしょう。
- 集計結果を社内に公開し、改善計画を発表
- 改善後のフォローアップを実施
- 小さな成功事例(上司の声かけ、相談体制の改善など)を共有
“見える化”と“継続的改善”を繰り返すことで、社員は「この会社は本気で取り組んでいる」と感じられるようになります。
ステップ⑤ 日常会話から「ハラスメントリテラシー」を育てる
ハラスメント対策は制度だけでなく、日常のコミュニケーション文化で定着します。
例えば次のような取り組みを行うと、自然に意識が根づきます。
- 朝礼やミーティングで「敬意ある呼び方」をテーマにディスカッション
- 社内チャットでの呼称を「さん付け」で統一
- 月1回の「言葉づかいチェックデー」を設定
こうした小さな積み重ねが、安心して働ける文化の土台となります。
経営層が率先することが最大の防止策
どれだけ制度を整えても、トップが軽視すればすぐに形骸化します。
経営層自身が「ハラスメントを起こさない」「放置しない」姿勢を明確に発信し、
社員に対して「尊重と信頼を前提とした職場づくり」を約束することが重要です。
リーダーの一言が、組織全体の意識を変えます。
ハラスメント対策はコストではなく、企業ブランドを守る投資です。
第七章 ― まとめ ― 敬意ある言葉づかいが信頼を生む職場へ
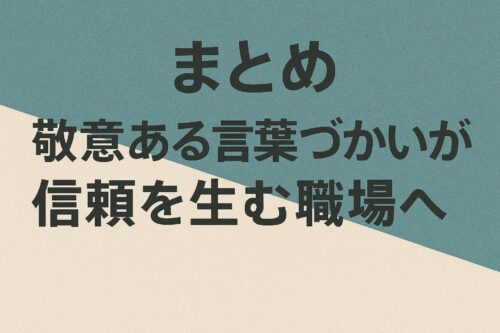
2025年の「ちゃん付け判決」は、日本社会に大きな問いを突きつけました。
それは、「あなたの言葉は、相手の尊厳を守っているか?」というシンプルでありながら、非常に重い問いです。
多くの人が「悪気はなかった」「昔からの習慣だった」と言い訳を口にします。
しかし、時代は変わり、価値観も変わりました。
いま社会が求めているのは、“意図よりも影響を考える”コミュニケーションです。
呼び方ひとつが信頼関係を左右する時代
「○○ちゃん」「お前」「女の子」——。
何気ない一言が、相手にとっては“見下し”や“性的なニュアンス”として伝わることがあります。
たった数文字の呼び方で、信頼を築くことも、壊すこともできる。
だからこそ、言葉の選び方に「敬意」を込めることが、ビジネスの基本マナーとなりつつあるのです。
職場は多様な人が協力しあう場です。
世代・性別・国籍・価値観が異なる人たちが集まるからこそ、言葉の距離感を丁寧に調整する力が求められます。
「さん付け文化」が信頼をつくる
結論から言えば、最も安全で、最も尊敬を伝えられる呼び方は「さん付け」です。
たとえ仲が良くても、職場では「○○さん」と呼ぶ。
それだけで、相手へのリスペクトとプロ意識が伝わります。
呼称の統一は、組織内の“対等な関係”を育て、
無意識の上下関係やジェンダーバイアスを取り除く効果もあります。
企業・個人に求められる意識改革
これからの企業は、「ハラスメント防止=リスク回避」ではなく、
「ハラスメント防止=信頼構築・生産性向上」と捉える必要があります。
- 管理職は「模範的な言葉づかい」でチームを導く
- 同僚同士は「フランクよりもリスペクト」を優先する
- 個人は「言葉が相手をどう感じさせるか」を常に意識する
この3点を徹底するだけで、職場の空気は劇的に変わります。
ハラスメントを“過去の言葉”にするために
「ちゃん付け」が違法と判断された今回の判決は、社会が成熟している証でもあります。
人の尊厳を守るために、私たち一人ひとりがアップデートし続ける。
その姿勢こそが、安心して働ける未来をつくる最も確実な方法です。
呼び方ひとつに、人格が現れます。
だからこそ、今日から意識してほしいのは——
“相手の名前に敬意を添える”というたった一歩。
それが、あなたの職場を「安心と信頼のある場所」へと変える第一歩です。