偽金販売事件とは何か
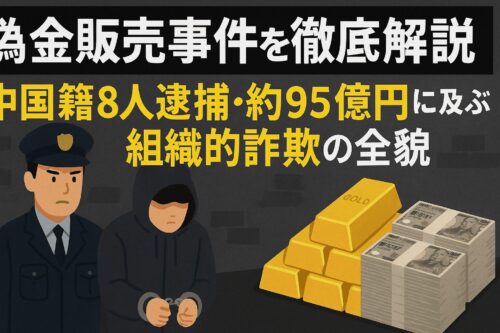
2025年、日本国内で大規模な詐欺事件として社会を揺るがせた偽金販売事件が摘発されました。
この事件は、東京都内の買取業者を狙い、偽造刻印が施された金塊を正規品として販売した組織的犯罪であり、警視庁が近年扱った中でも極めて悪質かつ大規模なケースとして注目を集めています。
事件が発覚したのは2025年1月中旬。
警視庁組織犯罪対策部は、会社役員の楊暁東容疑者(39歳)を含む中国籍の男女8人を逮捕しました。
主な逮捕容疑は、2025年3月〜4月にかけて、偽刻印入りの金の延べ棒 計37キログラムを買取業者に売却し、約6億円をだまし取ったことに関する詐欺容疑です。
しかし、事件の深刻さはこれだけにとどまりません。
警視庁の調べで、グループはわずか4カ月間(2025年3〜7月)で約95億円分の金を売却していた疑いが浮上しており、逮捕容疑は氷山の一角である可能性が極めて高いとされています。
偽金詐欺は金価格高騰に伴って世界的に増加している犯罪ですが、今回の事件は
- 金の偽造刻印
- 証明書の偽造
- 組織的な販売ルート
- 暗号資産を使った資金洗浄
など、複数の犯罪手法が組み合わさった高度な仕組みが特徴です。
本記事では、逮捕されたグループの特徴、詐欺の手口、マネーロンダリングの実態、そして再発防止に向けた課題について、事実に基づきながら専門的な視点で詳しく解説していきます。
逮捕された8人と事件の中心人物
偽金販売事件で逮捕されたのは、中国籍の男女8人です。
警視庁は、このグループが明確な役割分担のもとに行動していた組織的犯罪グループであるとみています。
なかでも中心人物とされるのが、会社役員の楊暁東容疑者(39歳)です。
事件の中心にいた楊暁東容疑者
楊容疑者は、偽金の調達、刻印加工、販売に関わる全体の指揮・管理役を担っていたとみられています。
買取業者との交渉窓口にも関わっていたとされ、
偽造金塊を正規品として売却するための「人物の選定」「証明書の準備」「信用工作」などの調整を行っていた可能性が高いとされています。
また、他の容疑者らは、
- 偽造刻印を施す担当
- 金塊の運搬担当
- 偽の書類作成担当
- 暗号資産への交換担当
など、それぞれが役割を分担して関与していたとみられています。
この点からも、今回の事件は単なる個人犯ではなく、組織として長期間にわたり綿密に計画された犯行であることが分かります。
グループの特徴
逮捕された8人は、いずれも日本国内で一定期間滞在し、
- 金の入手
- 販売ルートの確保
- 買取業者への接近
などを繰り返しており、日常的に活動していた痕跡があります。
また、警視庁は「背後にさらに大きな組織が存在する可能性」も視野に入れて捜査を続けています。
理由としては以下が挙げられます。
- 金塊の大量調達は単独では困難
- 偽造工具や刻印設備が高額で専門性が高い
- 暗号資産への資金洗浄には高度な知識が必要
これらを踏まえると、今回逮捕された8人は“実働部隊”であり、
背後で資金管理や運営を行う指示役が他にいる可能性も指摘されています。
偽金販売グループが用いた巧妙な手口

この事件が極めて重大とされる理由は、偽金の品質と偽装手口が非常に精巧であり、一見して見抜けないほど高度だったことにあります。
警視庁が明らかにした犯行の流れを整理すると、犯罪グループは複数の工程を組み合わせ、まるで本物の金取引のように見せかけていました。
偽造金塊の入手ルート
犯行グループは金塊の出所を明確に隠していましたが、捜査の結果、
- 特殊詐欺でだまし取った金塊
- 海外から密輸された金
などが使用されていた疑いが強まっています。
合法的に流通していない金塊を使用することで、トレーサビリティの追跡を困難にし、発覚を遅らせる狙いがあったとみられています。
大手貴金属会社の偽刻印を精巧に再現
偽装の核心は、金塊に施された偽のブランド刻印です。
大手貴金属会社の正規品に似せた刻印を独自の機械で打ち込み、
肉眼ではほとんど判別がつかないレベルで精巧に作り込まれていました。
- 刻印の位置
- フォント
- 深さ
- 金塊表面の加工痕
これらを限りなく本物に近づけることで、買取業者が通常行う目視鑑定では偽物と判断できなかったとみられます。
偽造した明細書や証明書を添付
このグループは、金塊本体だけではなく付属書類まで偽造していました。
特に、
- 商品明細書
- 品質証明書
- 買取履歴を偽造した書類
などを準備し、書類の真贋を確認しにくい買取業者の弱点を突いています。
書類のフォーマットも本物を模倣しており、業者が疑う余地を減らす効果を持っていたとみられます。
都内の複数業者に分散して販売
犯行グループは1つの店舗に集中して金塊を売るのではなく、
複数の買取業者に少しずつ販売する手法を取っていました。
これは以下の二つの目的を持つ典型的な詐欺手法です。
- 一度に大量の金塊を持ち込んで不審がられることを避ける
- どこかの業者で偽物が発覚しても全体の流れを止めないためのリスク分散
結果として、2025年3〜4月だけでも37kg、約6億円分の金塊を売り抜いています。
極めて巧妙な「本物に見せかける構造」
今回の事件に共通するのは、本物に近づけるための徹底的な演出です。
- 金塊を本物と見誤る刻印
- 本物と誤認する書類
- 時期を分けて売却する慎重な行動
- グループによる役割分担
これらが組み合わさることで、犯罪が長期間発覚しにくい構造になっていました。
約4カ月で95億円に膨れ上がった金販売の実態
偽金販売事件の衝撃は、逮捕容疑となった37キログラム・約6億円分の偽金だけではありません。
捜査が進む中で明らかになった事実は、さらに深刻でした。
警視庁の調べによると、このグループは 2025年3月〜7月の約4カ月間で、総額95億円分の金塊を売却していた可能性 が浮上。
これは逮捕容疑の約15倍以上という、近年でも例を見ない規模です。
ここでは、なぜ数カ月という短期間で、これほどまでに巨額の売却が可能だったのか、その背景を専門的な観点から解説します。
金価格の高騰で売却需要が拡大していた
2025年当時、世界的に金価格は過去最高水準に達していました。
投資家・企業・個人の間で「金を売りたい」という需要が急増していたため、買取市場は非常に活発な状況でした。
- 金価格が上がる → 買取業者は積極的に仕入れる
- 個人・法人が売却に訪れる → 業者は大量の金を日常的に扱う
この状況が、偽金を紛れ込ませやすい環境を作り出していたと考えられます。
買取業者が“スピード重視”だったことが盲点に
金価格が日々変動していたため、買取業者は迅速な対応を求められていました。
- 鑑定に時間をかけると金価格が下落する
- 他店に顧客を奪われるリスク
- 高額買取を強みとする店舗は即日査定が必須
このような背景から、通常より鑑定プロセスが簡略化されていた可能性も指摘されています。
偽造刻印や偽造書類が精巧だったことも重なり、業者が見抜くことは難しかったといえます。
グループが複数の業者に分散して売却
大量の金塊を扱うと疑われるため、一つの業者だけで売ることは避けていました。
犯行グループは、都内の複数店舗に少量ずつ売却する“分散型売却”を徹底しています。
これにより、
- 業者ごとの検品体制の違い
- 情報共有の遅れ
- ネットワークの分断
といった隙を突くことに成功しました。
結果として、複数店舗が偽金を買い取る状況が続き、短期間で売却合計が巨額に達したとみられます。
偽金の品質が極めて高く、発覚が遅れた
今回使用された偽金は、見た目や重量だけでなく刻印まで本物に近づけており、
通常の店舗レベルの鑑定では判別が困難でした。
また、偽造書類の質も高く、
「正規ルートで仕入れたもの」と信じ込ませるだけの説得力がありました。
そのため、偽物だと発覚したのは相当量の金が市場に流通した後であり、
これが被害額を拡大させた大きな要因となっています。
犯行グループの“回転速度”が異常に速かった
売却→換金→暗号資産へ交換→次の金塊売却
という一連の流れが非常に高速で行われており、
警視庁は「綿密な運用マニュアルが存在していた可能性」を指摘しています。
短期間でこれほどの回転を続けるには、
- 金塊の確保
- 加工
- 運搬
- 売却
- 資金移動
など多くのステップが必要ですが、それが途切れることなく行われていた点から、
背後にさらに大規模な組織が存在する可能性も捜査の焦点となっています。
暗号資産に換金されていた資金洗浄の実態

偽金販売事件の核心のひとつが、詐取した現金の大部分が暗号資産に換金されていたという点です。
この事実は、事件が単なる金詐欺にとどまらず、高度なマネーロンダリング(資金洗浄)を伴う国際的犯罪である可能性を示唆しています。
ここでは、警視庁が把握している資金移動の流れをもとに、犯罪グループがどのように資金洗浄を行っていたのかを整理して解説します。
詐取した現金は即座に暗号資産へ
金塊の売却によって得た数億〜数十億円規模の現金は、
短期間のうちに暗号資産取引所へ送金されていたことが判明しています。
暗号資産が選ばれた理由としては、以下の点が挙げられます。
- 資金移動のスピードが速い
- 国境を簡単に越えられる
- 少額に分割して送金できる
- 実体経済と切り離しやすい
- 中継アドレスを利用することで追跡が困難になる
特に、数十億円規模の資金を現金のまま持ち運ぶことはリスクが高いため、
暗号資産は犯罪者にとって“最も効率の良い資金逃避手段”となっていました。
マネロンの典型例「分割送金」と「ミキシング」
暗号資産を使ったマネーロンダリングでは、以下の手法が一般的です。
1. 分割送金(スモーフィング)
一度に大金を動かすと検知されやすいため、
数十〜数百の小口に分けて送金することで追跡を困難にする手法です。
犯行グループも、売却額の一部を複数の口座に少額で移し続けていました。
2. ミキシングサービスの利用
複数の資金を混ぜ合わせて誰の資金かわからなくする「ミキサー」と呼ばれる技術です。
一旦ミキサーに入れることで送金元と送金先の関連性が消え、
資金の“足跡”がほぼ消失するため、犯罪者が多用する手段です。
警視庁は今回の事件でも、こうしたサービスが利用された可能性を調べています。
最終的な資金の行き先は海外か
暗号資産は国境を簡単に越えるため、
犯罪グループの資金の多くは海外のウォレットに移動している可能性があります。
- 海外の取引所
- オフショア地域のウォレット
- 高度に匿名化されたチェーン上
- さらに他の暗号資産へ交換
このようなルートを辿ることで、
最終的な資金の行き先を特定することが非常に困難になります。
警視庁も、資金の流れの一部はすでに海外へ流出しているとみて捜査を継続しています。
金塊詐欺と暗号資産マネロンの“組み合わせ”が危険
今回の偽金事件は、単に金の偽造販売にとどまらず、
- 偽造刻印による精巧な偽金
- 証明書の偽造
- 都内買取業者への分散売却
- 暗号資産による資金逃避
これら複数の犯罪が組み合わさった、高度に計画された組織犯罪であったことが浮き彫りになりました。
金の偽造は国内の犯罪で完結しますが、
暗号資産を利用した資金洗浄は、
国際的な犯罪ネットワークと結びつく可能性が極めて高く、
事件をより複雑で深刻なものにしています。
偽金詐欺が増加する背景と市場の脆弱性
偽金販売事件は今回の組織的な犯行だけでなく、
近年の金市場そのものの構造的な弱点が犯罪を増加させているという点でも重要です。
ここでは、なぜ偽金詐欺がここ数年で急増しているのか、その背景を事実に基づいて解説します。
金価格の高騰が犯罪を引き寄せている
近年、世界的に金価格が急上昇し、史上最高値を更新する日も珍しくありません。
投資用としても価値が見直され、売買量が増えたことで、金市場は非常に活発になりました。
この状況は犯罪者にとって魅力的であり、
「金が高い → 売却すれば即現金化できる → 犯罪の利益が大きい」
という構図が成立しています。
結果として、
- 偽造金塊の増加
- 密輸による金の流入
- 買取業者を狙った詐欺
など、金に関する犯罪が世界的に増えているのです。
買取市場の“スピード重視”が裏目に
金の買取市場では、価格変動に対応するため査定が迅速に行われます。
しかし、スピードが優先されることで、偽物を見抜くための徹底した鑑定が難しくなります。
- 短時間で査定が必要
- 顧客を待たせられない
- 競争の激化でスピード対応が当たり前
こうした環境は犯罪者にとって大きな隙となり、偽金詐欺を成功させる土壌を生みます。
偽造技術の進化が鑑定を困難に
偽金事件が増えている背景には、偽造技術の進化もあります。
例えば、
- 高精度レーザー刻印
- 金塊表面の加工技術
- 本物デザインの精密模倣
- 正規品の書類フォーマットの複製
このように、偽物の完成度が極めて高いため、
目視レベルの鑑定では判別がほぼ不可能なケースが増えています。
特に今回の事件では、
大手貴金属会社の刻印が本物そっくりに再現されていたことが、
発覚を大幅に遅らせる一因となりました。
現場の鑑定体制にも課題
買取業者によっては、十分な鑑定機器を持たない店もあります。
全ての店舗がX線検査や比重測定機器を備えているわけではなく、
外観チェックや書類の確認に依存するケースも少なくありません。
犯罪グループはこうした店舗の“技術差”を熟知しており、
鑑定が甘い可能性のある店舗を狙って持ち込むことで成功率を高めています。
国際的な犯罪ネットワークとの接点
金の密輸や偽造刻印などは、国内だけでは完結しないことが多い行為です。
今回の事件でも、金塊の入手や加工、資金洗浄など、
複数の工程で海外組織の関与が疑われています。
- 海外からの密輸
- 外国人グループの役割分担
- 暗号資産を利用した国際送金
これらが組み合わさることで、
偽金詐欺は単なる国内犯罪ではなく、国際犯罪の一部として捉える必要があるほど複雑化しています。
消費者・事業者が取るべき具体的な対策

偽金販売事件は、金市場全体に潜むリスクを浮き彫りにしました。
今後同様の被害を防ぐためには、一般消費者・投資家だけでなく、買取業者や事業者も適切な対策を講じる必要があります。
ここでは、誰でも実践できる「再発防止策」と「リスク管理のポイント」をわかりやすく解説します。
専門的な鑑定機器を備えた業者を選ぶ
金の真贋判定で最も重要なのは、鑑定機器の有無と店舗の技術レベルです。
特に信頼できる業者は、
- X線蛍光分析装置(XRF)
- 比重計
- 高精度顕微鏡
などを備えています。
これらの機器を扱う店舗は、外観だけではなく金の内部構造まで確認できるため、偽造金のリスクを大幅に減らせます。
消費者が金を売る場合も、
「鑑定のプロセスを見せてくれる」「機器が整っている」
といった点を重視することで、被害リスクを下げることができます。
刻印や証明書だけを信用しない
今回の事件では、刻印や証明書が巧妙に偽造されていたため、
書類だけで真贋を判断するのは危険であることが明らかになりました。
- 刻印の大きさ・位置
- 証明書のフォーマット
- 付属書類の印影
これらは比較的模倣しやすく、犯罪者に狙われるポイントです。
そのため、書類はあくまでも補助的な確認と捉え、
必ず 実物の鑑定結果を重視する習慣が必要です。
取引履歴や出所の確認を徹底
金塊など高額商品の売買では、
出所の確認や書類の整合性チェックが欠かせません。
特に買取業者は以下を徹底する必要があります。
- 複数の書類間の整合性を確認
- 不自然な価格・量に警戒
- 同じ人物が短期間で大量に売却するケースを記録
- 初見の顧客の場合は特に詳細を確認
法的にも、買取業者は本人確認義務・取引記録義務などが定められており、
適切な管理はリスク低減に直結します。
不審な取引には必ず「再鑑定」を行う
もし鑑定で少しでも違和感を覚えた場合、
- 別の鑑定機関に持ち込む
- 他店舗の専門家に判断を求める
といったセカンドオピニオンを取ることが重要です。
複数の鑑定で一致すれば真贋判定の精度が高まり、
逆に不一致であれば犯罪の可能性が浮上します。
買取業者の教育体制と管理体制を強化
今回の事件を踏まえ、業者側は以下の体制強化が求められています。
- 従業員への真贋鑑定トレーニング
- 偽造刻印を見抜くための研修
- 高額取引時の内部チェック
- 情報共有ネットワークの整備
特に、業界内での情報共有が迅速であれば、
同じ犯罪グループによる被害拡大を未然に防ぐことができます。
消費者も日常的に注意が必要
金を購入する一般消費者にとっても、
偽金は“自分とは無関係”ではありません。
- 安すぎる金の購入は危険
- 個人間取引は偽物リスクが高い
- 信頼できる販売店を選ぶ
- 投資目的なら保管証明や保証制度の有無を確認
こうした基本的な対策だけでも、偽金被害の確率を大幅に減らせます。
事件が社会に与えた影響と今後の捜査の焦点
偽金販売事件は、単なる詐欺事件に留まらず、日本の金市場・買取業界・国際犯罪対策に深い影響を及ぼす重大な事件として扱われています。
ここでは、この事件が社会にどのような影響を与え、今後の捜査がどこを焦点に進められていくのかを解説します。
日本の金取引市場に走った衝撃
今回の事件は、金価格が最高値圏にある中で起こったこともあり、
業界全体に大きな不安をもたらしました。
特に影響が大きいのは以下の点です。
- 偽物が流通している可能性があるという不信感
- 中小規模の買取業者が鑑定体制の見直しを迫られた
- 正規の金取引にも影響し、取引量が一時的に減少した地域もある
- 金の査定に時間をかけざるを得ず、店舗の対応効率が低下
金市場は信用が命であり、こうした事件はブランド価値に直接影響を与えるため、社会的なダメージは極めて大きいものとなりました。
買取業界の構造問題が浮き彫りに
この事件は、金買取市場の構造的な弱点を表面化させました。
- 鑑定体制のバラつき
- スピード査定を求められる業界慣習
- 書類のチェック体制の甘さ
- 情報共有不足
特に、個人経営の買取店や地方店舗では、
高額な鑑定機器の導入が難しいケースも多く、
今回のような偽金詐欺に対する防御力が低い状況があります。
この事件を機に、
鑑定機器の導入支援や業界内での情報共有網の強化
が求められるようになっています。
国際犯罪ネットワークの可能性
事件の規模と手口から、警視庁は
「背後に海外の組織が存在している可能性」
を強く視野に入れています。
理由としては:
- 金塊の大量入手には国際ルートが必要
- 偽造刻印の技術水準が異常に高い
- 暗号資産を使った資金移動の専門性
- 8人の役割分担が非常に明確
- 資金の一部が海外ウォレットに送金されている可能性
こうした要素は、単独犯や小規模グループでは達成が困難であり、
国際的な犯罪組織との関わりを示唆しています。
今後の捜査では、
海外捜査機関との連携や資金追跡が重要な焦点になると見られています。
暗号資産規制の強化議論へ
今回の事件では、詐取した現金が暗号資産に交換されていた点が特に問題視されています。
そのため、
- 暗号資産のKYC(本人確認)強化
- 不審取引の監視
- 取引所のチェックプロセスの透明化
など、規制強化の議論も進む可能性があります。
犯罪収益が暗号資産に逃げれば追跡は一気に困難になるため、
国際的にもマネロン対策が急務となっています。
再発防止に向けて求められる社会全体の取り組み
この事件を受け、社会全体が以下の点を見直す必要があります。
- 金市場の鑑定制度の底上げ
- 買取業者の教育体制強化
- 消費者への啓発活動
- 国際協力によるマネーロンダリング対策
- 犯罪組織の資金ルート遮断
偽金詐欺は一度流通すると被害額が莫大になり、
その影響は業界だけでなく一般消費者にも及びます。
今回の事件は、
「日本社会全体で対策しなければ防げない犯罪である」
ということを改めて示した出来事といえます。