1. TCB東京中央美容外科が9億円の追徴課税を受けた背景

日本全国にクリニックを展開し、美容医療業界で急成長を遂げたTCB東京中央美容外科ですが、その運営法人である医療法人社団メディカルフロンティアが、国税当局から約9億円の追徴課税を受けたことが明らかになりました。
この問題は、単なる税務上の申告漏れにとどまらず、美容クリニック業界全体の税務処理の在り方にも影響を与える可能性があります。
追徴課税の金額とその内訳
今回の追徴課税の総額は約9億円で、その内訳は以下のようになっています。
- 申告漏れ額:約8億円
- 過少申告加算税および消費税未納分:約1億円
国税当局は、2022年5月から2023年までの約4年間に遡ってメディカルフロンティアの税務調査を行いました。
その結果、一部の収益が適切に申告されておらず、特に消費税に関しても未納があることが指摘されました。
申告漏れの詳細と国税当局の指摘内容
主な問題点として、以下の2点が挙げられています。
- 雇われ院長を「個人事業主」として扱い、消費税の免除制度を利用していた
- クリニックごとに「雇われ院長」を配置し、それぞれが独立した個人事業主として申告する形を取っていた。
- 個人事業主としての開業から数年間は消費税が免除される制度を利用し、法人全体の納税負担を軽減していた。
- 業務委託費の計上による「利益の回収」
- 雇われ院長が一部の業務委託費を計上し、法人側に利益を戻す形を取っていた。
- 国税当局はこれを「実態のない取引」と判断し、申告漏れと指摘した。
このような課税の仕組みは、美容クリニック業界では珍しくないと言われています。
しかし、今回のTCBのケースはその規模が大きく、国税当局が厳しく指摘する結果となりました。
2. 雇われ院長制度の問題点と個人事業主扱いの実態
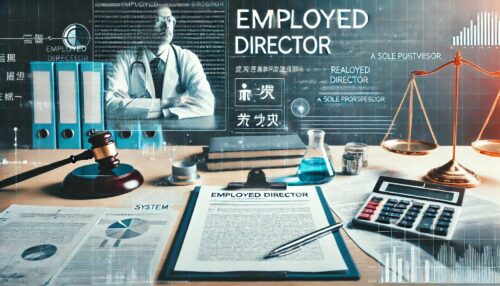
今回の追徴課税問題の背景には、TCB東京中央美容外科が採用していた「雇われ院長制度」が大きく関わっています。
本来、クリニックの院長は雇用契約のもと「従業員(勤務医)」として働くことが一般的ですが、TCBでは多くの院長が「個人事業主」として契約されていました。この契約形態が、税務問題を引き起こす原因の一つとなりました。
雇われ院長が「個人事業主」として扱われていた理由
TCBの雇われ院長は、実際にはクリニックの経営権を持たず、医療行為を提供する立場にすぎません。
にもかかわらず、「個人事業主」として契約されることで、以下のような仕組みが成り立っていました。
- 法人側の税負担を軽減
- クリニックの売上は本来、法人の収益として計上されるべきものですが、雇われ院長が「個人事業主」として契約することで、売上を院長のものとして申告できる仕組みになっていた。
- 個人事業主は、開業から2年間の消費税免除制度が適用されるため、その期間の消費税負担を抑えることができた。
- 院長の税務負担が増加
- 雇われ院長は、法人の従業員としての給与所得ではなく、個人事業主としての「事業所得」として確定申告する必要があった。
- 結果として、社会保険料の支払い義務がなくなる一方で、個人で税務処理を行わなければならないため、多くの院長が自らの税務状況を把握していなかった。
税務申告の責任を巡る問題
元院長の証言によると、雇われ院長の多くは「個人事業主として契約していることの税務的な影響を理解していなかった」とのことです。
- 「知らないうちに個人事業主として確定申告されていた」
- 院長の中には、法人側からの指示に従い、何も知らずに契約を交わしていたケースも多かった。
- 確定申告の際に問題が発覚し、税務署からの指摘を受けて初めて契約内容のリスクを知ることになった院長もいる。
- 業務委託費の扱いも問題視
- 一部の院長は、クリニックの売上から「業務委託費」として法人側に支払いを行っていた。
- しかし、国税当局はこの取引を「実態のない利益の回収」と判断し、課税対象とした。
このような雇われ院長制度の問題は、TCBに限らず美容クリニック業界全体で見直しが求められる課題と言えるでしょう。
3. 国税当局が問題視した税務処理の仕組み

TCB東京中央美容外科の運営法人であるメディカルフロンティアが受けた9億円の追徴課税は、単なる申告漏れではなく、国税当局が税務処理の仕組みそのものに問題があると判断した結果です。特に、以下の2つの点が厳しく指摘されました。
業務委託費の不透明な流れ
TCBでは、雇われ院長が「個人事業主」として契約し、クリニックの売上を一旦自身の事業収益として計上していました。
その後、「業務委託費」という名目で法人側に資金を戻す形を取っていました。
国税当局は、この業務委託費の流れを「実態のない利益の回収」と判断しました。具体的には以下のような問題点が指摘されています。
- 業務委託費として支払われた資金の使用用途が不透明
- クリニックの経営資金として必要な費用なのか、実態のない資金のやり取りなのかが不明瞭。
- 法人が納めるべき税金を個人の確定申告に転嫁
- 本来、法人の売上として申告すべきものを、院長個人の収入とすることで、法人の納税負担を軽減。
- 税務調査が入るまで多くの院長が認識していなかった
- 一部の院長は、契約上の問題点を知らずに業務を行っており、税務処理の責任を自分で負うことに気づいていなかった。
消費税免除制度の悪用が指摘された点
日本の税制では、新たに開業した個人事業主や法人に対し、開業後2年間は消費税の納付が免除される制度があります。
TCBの運営法人はこの制度を活用し、院長を個人事業主として扱うことで、クリニックの消費税負担を軽減していました。
しかし、国税当局は以下の点を問題視しました。
- 実態としては法人経営なのに、形だけ個人事業主として申告
- クリニックの経営権は法人が握っており、院長は実質的に「雇われている立場」に過ぎない。
- にもかかわらず、税制上は「個人事業主」として扱われていた。
- 一定の売上高を超えているにも関わらず、消費税を適正に納めていなかった
- 国税局の調査では、TCBの各クリニックの売上が、消費税の免除基準を大幅に超えていることが判明。
- にもかかわらず、開業から2年間の消費税免除制度を適用し続けていた。
このような税務処理の問題が明るみに出たことで、美容クリニック業界全体にも波紋が広がっています。
4. 美容クリニック業界全体への影響と今後の見直しの可能性

TCB東京中央美容外科の追徴課税問題は、美容クリニック業界全体に影響を与える可能性があります。
特に、同様の契約形態を採用している他のクリニックも、国税当局の厳しい監視の対象となる可能性が高まっています。
TCB以外のクリニックでも同様の契約形態があるのか
美容クリニック業界では、雇われ院長を個人事業主として契約するケースが少なくないと言われています。
- 節税対策として広く活用されていた可能性
- TCBと同様に、開業後2年間の消費税免除制度を活用するために、院長を「個人事業主」として扱うクリニックが多数存在すると考えられます。
- 税務処理のリスクを十分に認識していなかった可能性
- クリニックの経営側は「税制の範囲内で適切に運用している」と認識していたが、国税当局の見解では「実態のない契約」と判断されるケースも増えている。
- 今後、他の美容クリニックでも同様の税務調査が行われる可能性が高い。
国税当局の対応と今後の税制見直しの可能性
TCBのケースを受けて、国税当局は美容クリニック業界全体に対する監視を強化すると考えられます。
- 業務委託契約の厳格化
- 院長を「個人事業主」として扱う場合、本当に独立した経営判断を行っているかどうかが厳しくチェックされる可能性がある。
- 実態として法人が経営を管理している場合、法人側の責任として課税されることが増える可能性がある。
- 消費税免除制度の適用条件の見直し
- 現在の制度では、一定の売上を超えた場合でも、開業後2年間は消費税が免除される仕組みとなっている。
- しかし、今回の問題を受けて、「業態によっては消費税免除の適用範囲を狭める」などの見直しが行われる可能性もある。
業界全体の透明性向上への取り組み
今回の問題を受け、美容クリニック業界では税務処理の透明性向上が求められるようになるでしょう。
- 院長契約の明確化
- 雇われ院長が「個人事業主」として契約する際は、納税義務について十分な説明を行うことが重要。
- 確定申告のサポートや、税理士との連携を強化するクリニックが増える可能性がある。
- クリニック運営法人のガバナンス強化
- 法人側が税務リスクを回避するために、契約の見直しや税務処理の改善を進める必要がある。
- 国税当局の指摘を受け、業界全体で「従業員としての雇用契約に戻す」流れが出てくる可能性もある。
今回の追徴課税問題は、TCBだけでなく、美容医療業界全体にとって大きな転換点となる可能性があります。
5. TCBの対応と今後の展開

TCB東京中央美容外科を運営するメディカルフロンティアが受けた9億円の追徴課税は、業界全体に影響を与える大きな問題となっています。
今回の事態を受けて、TCB側はどのような対応を取るのか、今後の展開が注目されています。
運営法人メディカルフロンティアの対応策
追徴課税を受けたメディカルフロンティアは、今後、以下のような対応を進めていくと考えられます。
- 税務処理の見直しと再発防止策の実施
- 国税当局の指摘を受け、税務申告のルールを適正化し、過去の処理を見直す。
- 今後の契約形態を変更し、雇われ院長を「個人事業主」ではなく、従業員として雇用する方向に転換する可能性もある。
- 消費税免除制度の適用方法の変更
- これまでの消費税免除制度の利用が問題視されたため、今後はより適正な形で税務処理を行うことが求められる。
- 必要に応じて、専門の税理士や公認会計士と連携し、法的リスクを最小限に抑える努力が必要となる。
今後の信頼回復に向けた取り組み
今回の追徴課税問題により、TCBのブランドイメージにも影響が出る可能性があります。
そのため、信頼回復に向けた対策が急務となります。
- 透明性の確保と情報公開の強化
- 税務処理の適正化に加え、今後は企業の財務状況や契約形態に関する情報をより明確に公開することが求められる。
- 美容医療業界全体の信頼性を高めるために、ガバナンス強化やコンプライアンス体制の整備が必要となる。
- 従業員や雇われ院長へのサポート強化
- これまで院長たちが契約内容を十分に理解しないまま個人事業主として扱われていた問題が指摘された。
- 今後は、クリニック側が適正な税務知識を提供し、院長やスタッフが適正な契約形態で働ける環境を整えることが求められる。
TCBの今後の経営への影響
9億円の追徴課税は、TCBにとって大きな打撃となる可能性があります。
- 資金繰りや経営戦略への影響
- 9億円という額は、TCBの運営法人にとって決して小さな負担ではありません。
- これをどのように補填していくのか、今後の資金繰りに注目が集まる。
- 美容クリニック業界での立ち位置の変化
- 今回の問題によって、TCBに対する国税当局の監視が強まり、事業運営の自由度が低下する可能性がある。
- 競合他社との間で、経営戦略の見直しが必要になるかもしれない。
まとめ:業界の今後を左右するTCBの対応
今回の追徴課税問題は、TCB東京中央美容外科だけの問題ではなく、美容医療業界全体のビジネスモデルを見直す契機となる可能性があります。
今後のTCBの対応次第では、同様のビジネスモデルを採用している他のクリニックにも影響が波及するでしょう。
今後、TCBがどのような経営方針を打ち出し、信頼回復を図っていくのかに注目が集まります。