はじめに|なぜG検定は「用語マスター」が合否を分けるのか
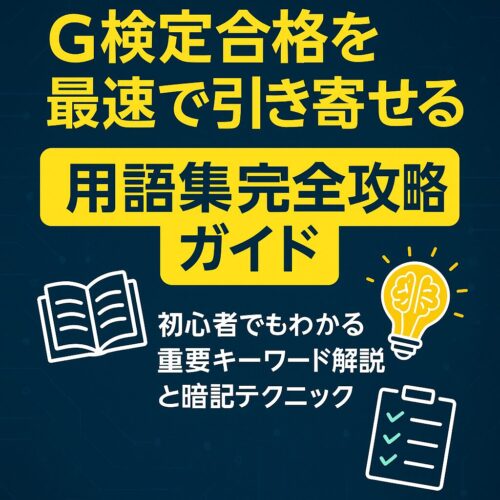
◆ シラバスが“攻略マップ”だからです
G検定の公式シラバスは、出題範囲をキーワード単位で明示しています。
つまり「ニューラルネットワーク」「GDPR」など書かれている言葉=試験問題になる可能性が高いということです。
逆に言えば、この用語を押さえれば“どこから撃たれても当たらない防弾チョッキ”を着るのと同じ──本番で読み慣れない単語に怯えることがなくなります。
◆ 30%超を占める“確定スコア源”
公式過去問を分析すると、選択肢・穴埋め・正誤判定など用語問題が全体の30〜35%を占めます。
計算問題や長文シナリオは試験ごとに難易度が上下しますが、用語問題の難度は「覚えたか/覚えていないか」で決定。
—覚えていれば100%正解—
この取りこぼしゼロの領域を先に固めることで、合格ボーダー(およそ65%)を一気に越えられます。
◆ 用語理解が“読む→わかる→解ける”を加速させる
- 読む:設問文をスムーズに読めるためタイムマネジメントが楽になります。
- わかる:概念同士の関連が見えるので、ひっかけ問題に強くなります。
- 解ける:応用問題(例:ビジネス活用シナリオを選択)も“用語→意味→答え”のショートカットで高速解答できます。
◆ 忙しい社会人こそ「用語ファースト学習」が最短ルート
仕事・家事・学業で時間が限られている方は、まずシラバスの見出しをチェックリスト化し、出勤中や家事の合間に「キーワード→一言定義」を口頭でリピートしてみてください。
たった5分でも“脳内フラッシュカード”を回せば、週末の学習効率が劇的に向上します。
✔ この章のキーメッセージ
- G検定は用語を覚えれば30%以上が確定得点になる。
- シラバス=攻略マップ。キーワード暗記が試験全体のタイムセーブにつながる。
- 忙しい人ほど“用語ファースト学習”でスキマ時間を最大活用。
それでは次章から、合格者が必ず押さえている頻出キーワードを分野別に深掘りしていきます。
まずは「機械学習・深層学習」の重要ワードを見ていきましょう。
G検定頻出用語集|これだけは覚えておきたいキーワード

機械学習・深層学習関連
- ニューラルネットワーク:人間の脳を模した層状構造を持ち、特徴量を自動で学習するモデルです。
- 勾配消失:深いネットワークで逆伝播時の微分値が極端に小さくなり、学習が止まってしまう現象です。
- 活性化関数:層間に非線形性を導入し、複雑なパターンを表現可能にする関数です(例:シグモイド、ReLU)。
- 過学習・汎化性能:訓練データにフィットしすぎると未知のデータで性能が落ちる現象と、その性能維持力を指します。
- バッチ正規化:ミニバッチごとに入力分布を標準化し、学習を安定かつ高速に進める技術です。
- ドロップアウト:訓練時にランダムにノードを無効化し、過学習を防ぐ手法です。
- 転移学習:既存モデルの学習済みパラメータを流用し、少量データで高精度モデルを短時間で構築する方法です。
統計・データ処理関連
- 損失関数:モデルの予測誤差を数値化し、最小化を目指す指標(例:平均二乗誤差、交差エントロピー)。
- 最尤推定:データが最も起こりやすくなるモデルパラメータを確率論的に求める手法です。
- 混同行列:分類結果の真陽性・偽陽性・偽陰性・真陰性を整理し、各種指標算出の基盤となる表です。
- 精度(Precision):陽性と予測した中で正しく陽性だった割合を示す指標です。
- 再現率(Recall):実際に陽性の中で正しく陽性と予測できた割合を示します。
- F値(F1 Score):精度と再現率の調和平均。両者のバランスを評価します。
- ROC曲線/AUC:偽陽性率と真陽性率の関係をプロットし、その下の面積で分類性能を評価します。
AI社会実装・倫理・法規制
- AIバイアス:データの偏りや設計ミスで特定グループに不利な判断を行う問題です。
- GDPR:EU一般データ保護規則。個人データの取り扱いに厳格な罰則を定めています。
- アカウンタビリティ:AIの判断責任を明確にし、説明可能性を担保する概念です。
- プライバシーバイデザイン:システム設計段階からプライバシー保護を組み込むアプローチです。
- フェアネス(公平性):属性に依らず公正な判断を行うための評価・改善手法全般を指します。
- AIガバナンス:倫理・法規制・技術リスクを組織的に管理・運用する体制とプロセスです。
◆ この章のポイント
- まずは上記15キーワードを「見て→言って→書いて」覚えましょう。
- 「一言説明」が即答できれば用語問題で満点を狙えます。
用語の意味をやさしく解説|初心者でもイメージできるまとめ
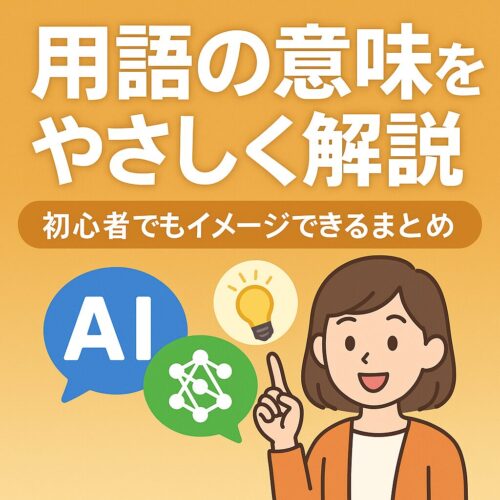
ここまで並べた用語を、さらに直感的にイメージできるように解説します。
ニューラルネットワークは「水道管と蛇口」
水道管(層)を通じて水(情報)が流れ、 蛇口(活性化関数)で「出る量」を調整します。
多層にすると、水が複雑に混ざり合って「高精度な出力」が得られます。
勾配消失は「遠くの声が小さく聞こえる」
深い山(ネットワーク)を越えてメッセージを伝えると、 途中で声がだんだん小さくなって聞こえなくなるように、 誤差(勾配)が伝わりにくくなって学習が止まってしまいます。
バッチ正規化は「クラス全員でストレッチ」
体育の前にクラス全員でストレッチすると、 体がほぐれて動きやすくなりますよね。
バッチ正規化もミニグループごとにデータを整え、 学習速度と安定性を高める“ウォームアップ”です。
損失関数は「ゴールまでの距離を測る定規」
走り幅跳びで距離を測る定規のように、 モデルの予測と正解のズレを数値化します。
赤点(損失)が小さいほど、ゴール(高精度)に近いです。
混同行列は「赤・白ワインのテイスティング表」
テイスターが赤を白と判断したり、白を赤と間違えたりする数を、 4マスに整理します。
これにより「どの間違いが多いか」が一目瞭然です。
GDPRは「図書館の貸出ルール」
本(個人データ)を借りるとき、返却期限や貸出記録を厳格に管理します。
違反すると罰金(高額ペナルティ)が科される、 “厳しい貸出ルール”としてイメージしてください。
AIバイアスは「歪んだ地図」
偏ったデータで作った地図は、特定地域が異様に広く見えます。
その地図を頼りに進むと、思わぬ遠回りや行き止まりに遭うように、 偏りデータはAI判断をゆがめます。
◆ この章のポイント
- 専門用語を「身近なもの」に例えると、頭に残りやすいです。
- ストーリーや比喩を加えるだけで、理解度も定着度も格段にアップします。
G検定用語の覚え方|暗記が苦手な人へのコツ
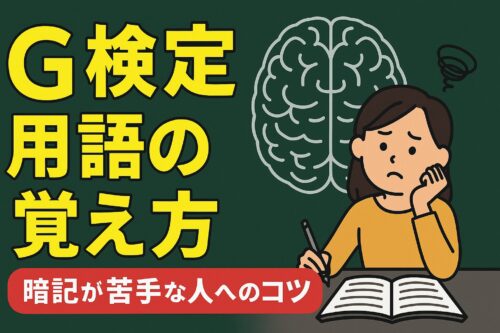
丸暗記だけでは脳のキャッシュがすぐに消えてしまいます。
ここでは「理解」「関連付け」「反復」を組み合わせた暗記テクニックを紹介します。
◆ 1. ストーリー法で記憶に定着
- 用語をキャラクター化して物語を作ります。例:「バッチ正規化くん」は毎朝クラスを整列させる先生役。
- ストーリーを音読するだけで、用語と機能がセットで脳にインプットされます。
◆ 2. 自分の言葉でノート化
- 公式定義をそのまま写すのはNG。
「過学習」→「先生の宿題を完璧に覚えすぎて、新テストで問題が変わると全く解けない状態」など、自分目線に翻訳しましょう。 - 手を動かすことで記憶が強化されます。
◆ 3. フラッシュカード&アプリ活用
- 用語と一言定義を表裏に書いたカードを作成。
スキマ時間にシャッフルして何度もめくります。 - AnkiやQuizletなどのSRS(間隔反復)アプリを使うと、忘却曲線に合わせた復習スケジューリングが自動化できます。
◆ 4. 問題集を使ったアウトプット重視
- 「用語→選択肢/穴埋め問題」を解く→解説を読み、自分の言葉で再解説→再チャレンジ。
- 間違えた問題は見開きノートにまとめ、翌日・3日後・1週間後に再テスト。
◆ 5. 友人や家族への口頭説明
- 「教えることは学ぶこと」といわれるように、人に向かって用語を説明すると理解度が格段に深まります。
- ZoomやLINE通話でクイズ出題すれば、楽しく記憶が定着します。
◆ この章のポイント
- ただ読む→書くではなく、「ストーリー化」「反復テスト」「人に説明」を組み合わせると効率的。
- 自動化ツール(Ankiなど)を活用すると、復習タイミングを逃しません。
G検定シラバスに載っているその他の用語例
- エントロピー:情報の不確実性を測る指標。分類モデルの分岐条件で使われます。
- トランスフォーマー:自然言語処理で長文の依存関係を高速に学習するモデルアーキテクチャです。
- フェデレーテッドラーニング:複数端末で局所学習し、モデル重みのみ集約してプライバシーを守る分散学習方式です。
- MLOps:機械学習モデルの開発から運用までをCI/CDパイプラインで自動化・監視する実践手法です。
- LLM(Large Language Model):数十億〜数兆パラメータを持つ大規模言語モデル。GPTシリーズなどが代表例です。
- カーボンフットプリント:AI学習・推論時のCO₂排出量を定量化し、環境負荷を可視化する指標です。
- 説明可能AI(XAI):ブラックボックスモデルでも判断根拠を可視化・説明する技術群の総称です。
シラバスを学習ロードマップとして使うコツは、用語一覧を章ごとにチェックリスト化し、「学習→チェック→理解度★評価」を繰り返すことです。
未チェックの用語は週末学習、★1の用語は翌日復習など、スケジュールを組むと抜け漏れが防げます。
G検定に出る用語の頻度や重要度はどのくらい?
G検定全体の出題構成を振り返ると、用語問題は約30〜35%を占めています。
特に以下のポイントを押さえておきましょう。
- 高頻度ワードは毎回必ず出る
ニューラルネットワーク、損失関数、GDPRといった基礎キーワードは過去問でも8回中7回以上登場しています。 - 中頻度ワードはテキスト中盤以降に出題
バッチ正規化、ROC曲線、AIバイアスなどはシラバス中段以降に記載されており、ここを押さえると安定して得点できます。 - 低頻度ワードは補助スコア源
フェデレーテッドラーニングやカーボンフットプリントなどは1〜2問程度ですが、覚えていれば「差」がつきます。
重要度の高い用語は二次利用問題(用語を用いた応用設問)にも出現しやすいため、「覚える→理解する」ことで、選択肢問題もケース問題も一気に得点アップできます。
用語を覚えるコツ|理解+アウトプットで最短合格
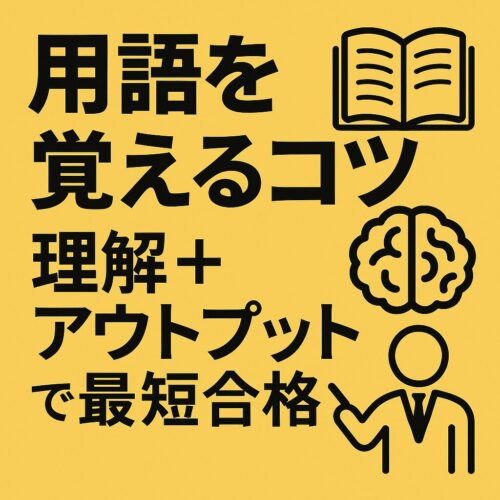
用語学習は「ただ覚える」だけでは定着しにくいため、理解→アウトプット→復習のサイクルを確立しましょう。
- シラバス全体をざっと把握
まず見出しと用語一覧を眺め、「今日はこの章」「明日はあの章」と大まかな学習計画を立てます。 - テキスト・動画で概念理解
新出用語は図解やイラスト、動画講義でイメージを掴みます。理解が曖昧なまま暗記すると応用問題で行き詰まります。 - 問題集や模試でアウトプット
用語問題集を解き、間違えた用語はノートに書き出します。同時に「なぜそれが正解か」を自分の言葉で説明してみましょう。 - 48時間以内に復習
人間の忘却曲線に合わせ、初回学習後24~48時間以内に再テストします。ここでの復習が合格率を大きく左右します。 - 合格圏に入ったら模試反復
模擬試験を最低2回、本番タイマー(120分)で回します。全問解いた後は必ず間違い分析と用語チェックを実施。
◆ この章のポイント
- 用語学習は「理解+アウトプット+復習」の3ステップで定着する
- 48時間以内の再テストを必ず組み込むことで記憶を長期化
- 模試はタイマー付きで実践感覚を鍛え、間違い分析を徹底する
まとめ|G検定は用語理解が合格への最短ルート
- 用語学習は試験全体の30%以上の確定得点源です。
- 公式シラバス=キーワード攻略マップ。まず目次をチェックリスト化しましょう。
- ストーリー化・自分語りノート・フラッシュカードの3手法で「理解→定着→瞬発暗記」を実現。
- 48時間以内の復習とタイマー付き模試で忘却曲線を攻略し、知識を長期記憶化します。
- 用語の「覚える→意味がわかる→説明できる」状態を目指せば、応用ケース問題でも時間短縮&高得点。
- 本記事のチェックリストを活用し、毎日の進捗を「見える化」すると挫折しません。
用語マスターは合格への“最短バイパス”です。今日からシラバスを開き、この記事の手順で学習を進めてください。
用語を押さえれば、G検定合格への扉はすぐそこにあります。
ちなみに無料で使えるG検定の用語チェックアプリがあります。
>まずはこちらからあなたの理解度をチェックしてみてください👇
\タダで簡単10秒!/