第一章 はじめに 〜26年の連立に終止符〜
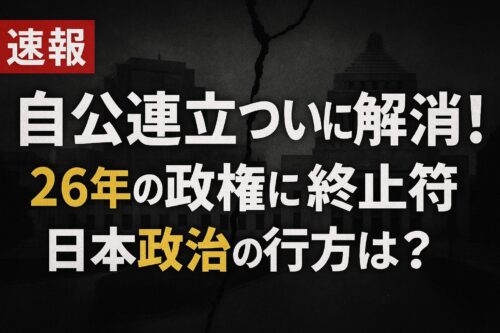
2025年10月10日、日本政治において歴史的な転換点が訪れました。
自民党と公明党による連立政権が、26年ぶりに解消されたのです。
1999年の連立開始以来、両党は国政運営の中心を担い、衆参両院での安定多数を背景に長期政権を維持してきました。
しかし、その“盤石”と思われた体制がついに終焉を迎えました。
公明党の斉藤鉄夫代表は10日午後、東京・永田町で行われた党首会談において、自民党の高市早苗総裁に対し「連立政権からの離脱」を正式に通告。
会談は約1時間半に及び、両党の幹事長も同席する中、26年間続いた協力関係に幕が下ろされました。
歴史的連立の終わりが意味するもの
自公連立は、1990年代後半の政局混迷期に誕生しました。
以来、両党は選挙協力や法案運営で緊密な関係を築き、長期政権を維持する政治の「安定軸」とされてきました。
しかし、今回の解消劇は単なる“関係悪化”ではなく、
政治とカネをめぐる倫理観の断層が背景にあります。
- 公明党が主張する「企業・団体献金の透明化」
- 自民党の裏金問題に対する不十分な説明責任
- 政治倫理法改正をめぐる歩調のズレ
これらが積み重なり、最終的に公明党側が「国民の信頼を守るためには離脱しかない」と判断しました。
自民党・公明党双方への衝撃
連立解消の報は永田町に激震を走らせました。
自民党は現在、単独での過半数維持が難しい構造にあり、公明党の支援なしでは国会運営にも支障が出る可能性があります。
一方の公明党は、26年間築いてきた与党としての地位を手放す決断を下したことで、支持基盤との再構築が急務となります。
特に創価学会関係者の間では、
「信念を貫いた英断」と評価する声と、
「長年の関係を失うリスク」への不安が交錯しています。
日本政治に走る“再編”の波
自公分離によって、日本の政党勢力図は大きく塗り替えられようとしています。
自民党は今後、国民民主党や日本維新の会など中道勢力との連携を模索するとみられます。
一方、公明党は政策ごとに協力を判断する“是々非々”路線へ移行し、野党として新たな立場を確立する方針を示しています。
今回の決裂は、単なる連立解消ではなく――
戦後政治の枠組みが根底から変わる“再編の序章”といえるでしょう。
次章では、
この歴史的な連立解消がどのような経緯で決定に至ったのか。
その裏にあった「政治とカネの問題」と「信頼の亀裂」を、事実ベースで詳しく解説します。
第二章 連立解消の経緯と背景
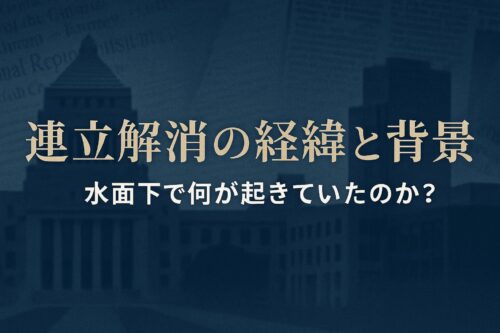
10月10日、自公連立は正式に解消される決定がなされました。
その背景には、長年の協力関係に潜んでいた価値観のズレと、特に「政治とカネ」をめぐる対応の違いが決定打となりました。
「離脱」表明までの流れ
- 公明党の斉藤鉄夫代表はこの日、自民党の高市早苗総裁と党首会談を行いました。
そこで、連立維持についての協議を続けたものの、折り合いはつかず、離脱を正式に通告しました。 - 会談は約1時間半に及び、両党の幹事長も同席する中で、具体的な議論が持たれました。
- 斉藤代表はその後、記者会見で「関係を一度白紙に戻す」「国民の信頼を回復するための決断」などの言葉を述べ、単なる関係修復ではなく区切りをつける意向を示しました。
この過程は、連立を維持するための話し合いが最終段階まで続けられたことを示しています。
しかし、公明党側が求めた政策的・倫理的要請と、自民党側の応答には大きな隔たりがあり、それが決裂の直接原因となりました。
決定的な理由の核心 ― 政治とカネの問題
連立解消の最も大きな要因は、公明党と自民党の間で裂けた「政治とカネ」に関する姿勢の違いです。
具体的には以下の点が焦点となりました。
- 企業・団体献金規制の強化
公明党側は、企業・団体からの政治献金に対する規制強化や透明性向上を求めていました。
これに対して自民党側の対応が十分ではないと判断されました。 - 裏金問題・説明責任の在り方
自民党の内部で浮上していた裏金や不透明な資金流れに対する説明責任を強く問う声が公明党側にありました。
その説明内容や対応が「誠に不十分」と公明党が評価したことが、離脱の決定打となりました。 - 応答の姿勢・信念の違い
公明党は、政策遂行・政治倫理の観点から慎重で透明な対応を重視してきました。
自民党側の改革対応では、公明党の信念と整合しない部分が次第に目立つようになりました。
これらの要素が重なり、最終的には協力関係の継続が「党としての信頼や理念を骨抜きにする」と判断され、決断的な離脱へと至ったのです。
長期連立の陰にあった“価値観のズレ”
連立政権が長年続いた背景には、選挙協力や政策面での利害調整といった現実的な合意もありました。
しかし、その基盤が揺らぎ始めた要因はむしろ日常的な政策判断や倫理観のズレにあります。
- 公明党の支持基盤である創価学会は、信仰的価値観や“政治倫理”を重視する構成員が多いとされてきました。
- 自民党は国政運営上、現実的な政策調整・妥協を重ねなければなりません。これが、理念優先・倫理重視志向との摩擦を生んできた側面があります。
- 特に、政治資金・献金制度・説明責任という“見えにくい”が根本的なテーマで、公明党が党の存亡・信頼回復を掲げて主張を強めたことが、離脱の引き金となりました。
こうした価値観のズレは、表向きには目立ちませんが、長年の信頼関係を徐々に浸食していったと見ることができます。
このように、連立解消は「単なる政局の変化」ではなく、長年の積み重ねから生じた理念と倫理の乖離の結果であると言えます。
第三章 国会運営と政権基盤への影響
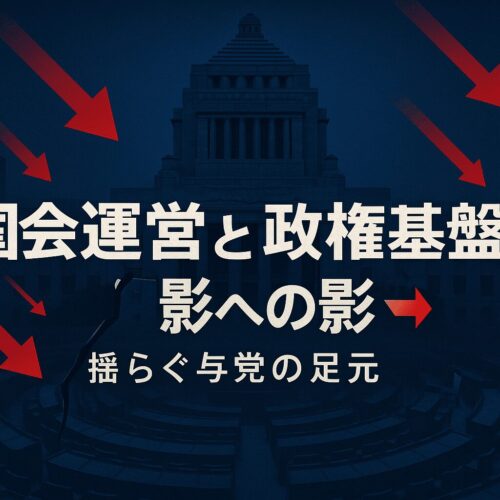
自公連立の解消は、単なる政治的パートナーシップの終了ではなく、日本の国会運営そのものに直撃する事態です。
ここでは、議席構成、法案審議、政権運営、次期政局の4つの視点から、その影響を具体的に見ていきます。
1. 与党の「過半数割れ」リスク
2025年10月現在、衆議院・参議院ともに自民党単独では安定多数を確保していません。
これまで公明党との連立によって政策運営が支えられてきましたが、離脱によって衆院・参院双方での法案可決が困難になることは避けられません。
- 衆議院では、自民単独で「絶対安定多数(261議席)」を下回る
- 参議院では、公明党の票がなくなることで過半数割れが確実
- 重要法案や予算案の成立に、他党との協力が不可欠に
この構造は、1993年の細川連立政権誕生前夜に似た「ねじれ構造の再来」を思わせます。
政権の舵取りは格段に難しくなり、“一強”から“多党調整型”への転換点を迎えました。
2. 国会運営への実務的影響
これまでの自公体制では、与党間の政策調整を経て法案提出までの流れがスムーズでした。
しかし今後は、次のような運営上の変化が生じると見られます。
- 与党内の「政策協議会」が廃止され、官邸主導の調整が中心化
- 法案審議における野党との事前交渉が増加
- 審議時間確保のための「会期延長」や「再可決」手続きが常態化
つまり、これまでの「自民+公明=安定運営」というモデルが崩壊し、国会はより不安定で流動的な環境になります。
今後は、**国民民主党・維新の会など中道勢力との“法案ごとの連携”**が鍵を握るでしょう。
3. 内閣基盤への圧力と再編シナリオ
高市早苗総裁率いる自民党政権にとって、この連立解消は“政治的試練”の始まりです。
支持率は下落基調にあり、党内では早くも「早期衆院解散」や「新連立構想」の声が上がっています。
考えられるシナリオは次の3つです。
- 維新・国民民主との連立構想
→ 政策面で親和性が高く、現実的な選択肢。 - 無所属・中堅議員との個別連携
→ 数合わせ的要素が強く、政権安定性に課題。 - 一時的な少数与党体制
→ 国会での法案審議が遅延するリスク大。
いずれにしても、高市政権は“単独政権の脆弱性”という構造的問題に直面しています。
官邸主導型から「連携と合意形成型」へのシフトが不可避です。
4. 公明党の立場と「キャスティングボート」化
一方、公明党は野党化しながらも、政策ごとの協力余地を残しています。
これは、国会運営において「是々非々のキャスティングボート」を握る立場になることを意味します。
- 社会保障・教育・環境政策などで協力する可能性
- 政権運営を支えるか、追い詰めるかの選択を随時行う立場
- 「対立より対話」という中道政党の立ち位置を強調
つまり、公明党は「完全な野党」ではなく、政局に応じて柔軟に立ち回る“政策型中道政党”へ変化していく可能性があります。
5. 今後の焦点
今後の政治スケジュールでは、20日以降の臨時国会で首相指名選挙が行われます。
この場で公明党は「斉藤鉄夫」と記載する方針を明言しており、これが**事実上の“決別宣言”**となります。
自民党はこの局面で、国民民主党との水面下交渉を加速させるとみられ、
「新しい中道連立」「限定的政策協定」など、さまざまな再編シナリオが動き始めています。
自公連立の解消は、単なる“政権の離婚”ではなく、
「日本政治の意思決定構造」そのものを再定義する出来事です。
次章では、選挙戦略の面から見た「選挙協力の崩壊と小選挙区の影響」を詳しく解説します。
第四章 選挙協力の崩壊と小選挙区のリスク
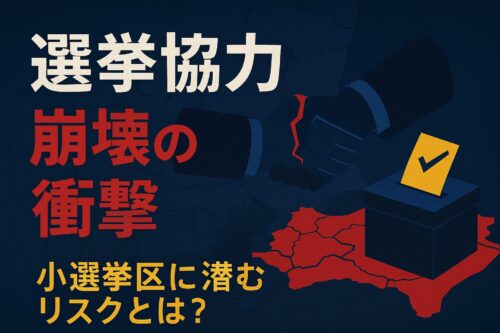
26年間続いた自公の選挙協力体制が崩壊したことで、次期衆議院選挙は「戦後最大級の勢力再編選挙」になる可能性があります。
自民党にとっては“地盤”を失い、公明党にとっては“存在意義の再定義”が問われる局面です。
1. 自公選挙協力の崩壊とは何か
自公の選挙協力は、1999年の連立発足以来「小選挙区の共闘」を中心に築かれてきました。
公明党が候補を立てない代わりに、自民党候補を支援する――その見返りとして比例区での自民票支援を得るという相互補完の構図です。
しかし今回、両党は明確に次の方針を打ち出しました。
- 自民党:「今後の小選挙区での相互推薦は行わない」
- 公明党:「人物本位・政策本位で独自候補を擁立」
つまり、今後の選挙では全国289の小選挙区で競合が発生する可能性があります。
特に都市部(東京・大阪・愛知・神奈川)では、票の分裂が致命的な結果をもたらします。
2. 自民党に迫る「2割落選リスク」
過去の選挙データをもとに試算すると、公明党の支援票(学会票)が失われることで、
自民党は全候補の約2割が落選リスクにさらされると見られます。
たとえば、前回衆院選(2021年)の小選挙区において:
- 公明党支援票が約8万〜10万票規模に達した地域では、自民候補の勝敗差が平均3〜4%
- 都市部の接戦区(例:東京12区、大阪6区、神奈川11区など)では、公明票の有無が“当落を決定づけた”実例が複数
この「学会票ロス」は、自民党にとって致命的です。
一方、公明党は比例代表で安定票を持ちますが、小選挙区に候補を立てれば“保守票分裂”による共倒れのリスクを抱えます。
3. 公明党の独自路線と“生存戦略”
公明党は「与党を離れても政策実現力を維持する」姿勢を強調しています。
今後の方針は次の3点に集約されます。
- 地域密着型の候補擁立
→ 全国的な戦いではなく、都市部・宗教支持基盤の強い地域で限定的に展開。 - 政策本位の選挙戦略
→ 教育・社会保障・福祉など“生活直結型政策”を前面に押し出す。 - 中道ブロック形成の可能性
→ 維新や国民民主との限定的な政策連携も模索。
この戦略は、「組織票+政策訴求」による“第三極的中道ポジション”の確立を狙ったものです。
4. 与野党再編の引き金に
自公の離別は、他党の動きにも大きな影響を与えます。
- 日本維新の会:都市部での保守票受け皿として勢力拡大を狙う
- 国民民主党:自民との限定連立・政策協定の可能性を模索
- 立憲民主党:反自民の一本化を狙うが、候補調整の難航が予想
これにより、次期総選挙は「自民vs野党連合」ではなく、
自民・中道新連立・リベラル連合・新興勢力の四極構造に移行する見通しです。
5. 創価学会票の行方
創価学会員の動向は、今後の選挙結果を大きく左右します。
学会内では、「公明支持を堅持する層」と「地域事情で自民を支援する層」がすでに分岐しつつあります。
このため、選挙現場では“地域ごとの選択”が発生し、これまでのような全国一律の支援体制は崩壊します。
結果として、自民・公明の双方にとって得票が読めない選挙になる可能性が高いです。
6. 次の焦点は「衆院解散のタイミング」
高市政権がこの混乱を乗り切るためには、政治主導で選挙の主導権を握る必要があります。
臨時国会後の年内解散、または2026年春の統一地方選に合わせた解散が取り沙汰されています。
しかし、世論調査では「自公分離を評価する」が過半数を超えており、
一方で「自民単独政権には不安を感じる」という回答も増えています。
この“民意の揺らぎ”をどの党が掴むかが、次期政権の鍵を握るでしょう。
自公の選挙協力崩壊は、
「組織票と地盤政治が終わり、個人・政策が勝敗を分ける時代の始まり」です。
次章では、この政変が経済と金融市場に与えた即時的なインパクトを、日経平均・為替・国債市場のデータをもとに解説します。
第五章 市場・経済への即時的反応

自公連立の解消という政治イベントは、瞬時に市場へ反応を引き起こしました。
政治と経済は密接に連動しており、特に日本のように政権安定が経済政策の基盤となっている国では、
「政権の不透明化=市場の不安定化」に直結します。
1. 株式市場 ― 日経平均先物が1,000円超急落
2025年10月10日午後、連立解消の報が流れると同時に、
日経平均先物は前日比1,180円安まで急落しました。
これは、政治リスクの高まりにより投資家がリスク資産から資金を引き上げた典型的な反応です。
背景には、次の3つの懸念があります。
- 政策継続性への不安:
これまでの“安定与党”による経済政策(財政支出・減税・企業支援策など)が停滞する可能性。 - 補正予算・税制改正の遅れ:
与党間調整が必要だった法案審議が混乱し、2025年度補正予算成立が遅延するリスク。 - 海外投資家の売り姿勢:
外国人投資家は日本市場を「安定政権前提の投資先」として捉えており、政局不安が出た瞬間に先物売りを強める傾向。
一時的な下げ幅としては、2022年の「安倍元首相襲撃事件」直後以来の規模となりました。
2. 為替市場 ― 円高方向への急変動
ドル円相場も連立解消の報道後、152円台前半まで円高が進行しました。
これは、市場心理が「リスク回避の円買い」に傾いたことを示しています。
通常、円は世界的に「安全資産」と見なされており、
政局が不安定化すると短期的に円が買われる傾向があります。
ただし、この円高は一時的な反応であり、
長期的には日米金利差が依然として大きいため、中期トレンドとしての円安傾向は継続しています。
つまり、今回の円高は「政治ショックによる瞬間的調整」であるといえます。
3. 債券市場 ― 国債先物が上昇
リスク回避姿勢の高まりにより、国債先物は約20銭上昇しました。
投資家が株式などのリスク資産から日本国債へ資金を移す“安全逃避”が起きた格好です。
この結果、長期金利(10年国債利回り)はわずかに低下しました。
ただし、財政拡大路線の見直しや政治的な予算審議の停滞が長期化すれば、
今後は「国債増発リスク」への懸念が再燃する可能性もあります。
4. 投資家心理の急冷
金融市場全体で見れば、今回の連立解消は「不確実性の再登場」として認識されました。
特に、海外ファンドや機関投資家の中では「高市政権の政策持続性」に対する疑念が浮上しています。
- 政権が安定しなければ、経済再生計画・防衛費増額・脱炭素投資などの中長期政策も停滞する
- 政策の一貫性が揺らぐことで、企業の設備投資や賃上げの momentum が鈍化する
つまり、市場の反応は「政権運営力」への信任低下と直結しているのです。
5. 今後の経済シナリオ
短期的には、政治不安を織り込んだ株安・円高が続く可能性があります。
しかし、中期的な展望では次の2つのシナリオが考えられます。
シナリオA:早期安定化で市場回復
- 自民党が新たな連立・協力体制を構築
- 補正予算や税制改正の方向性が示され、政治的空白が短期で収束
→ 株価は急反発し、日経平均は再び38,000円台を回復
シナリオB:政局混迷で長期調整局面
- 解散・総選挙の長期化、内閣支持率の低迷
- 景気刺激策の遅れ、円高・株安基調が続く
→ 景気回復の足を引っ張り、企業マインドが悪化
いずれにしても、鍵となるのは「政治的安定性をいつ取り戻せるか」です。
金融市場は、政治そのものよりも「見通しの明確さ」に反応します。
6. 経済への教訓
今回の一連の市場反応は、日本経済に次の教訓を突きつけています。
- 政治の信頼は「最大の経済政策」である
- 政治的混乱は、投資家心理と実体経済の双方に悪影響を及ぼす
- 中長期的な成長戦略を維持するには、安定的な政治基盤が不可欠
つまり、自公連立の解消は単なる政治のニュースではなく、経済基盤の再定義を迫る出来事なのです。
次章では、創価学会および公明党支持基盤の反応を中心に、社会的・宗教的側面からこの出来事の意味を整理します。
政治だけでなく「信仰と組織の動き」が、今後の日本政治をどう変えていくのかを見ていきます。
第六章 創価学会・支持層の反応
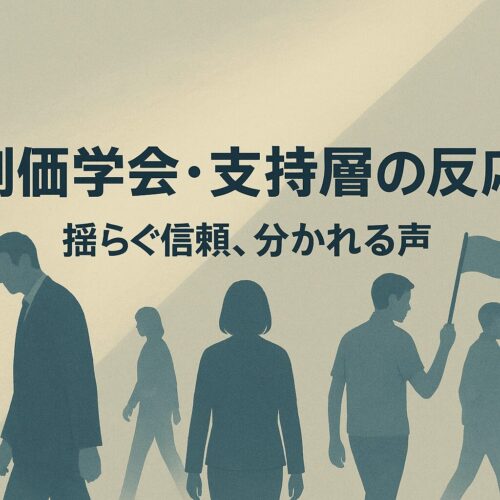
自公連立の解消は、単なる政党間の決裂ではありません。
それは同時に、公明党の最大の支持基盤である創価学会の政治的立ち位置にも大きな影響を及ぼしました。
宗教団体としての信条と、現実政治との関係性――そのバランスが今、根本から問い直されています。
1. 支持母体・創価学会の“複雑な静けさ”
連立離脱の発表直後、創価学会本部はコメントを控え、冷静な対応を見せました。
しかし、現場レベルでは次のような反応が広がっています。
- 「ようやく筋を通せた。誠実な決断だ」との肯定的評価
- 「長年の信頼関係を壊すことになるのでは」との不安の声
- 「政治離れを避けるため、慎重な再構築が必要」との意見も
特に地方組織や婦人部などでは、地域社会での“選挙協力”が生活レベルで浸透しており、
突然の関係断絶は心理的にも大きな戸惑いを生んでいます。
2. 学会内部における“理念と現実”の葛藤
創価学会は戦後一貫して、「人間主義」「平和」「福祉」を政治理念の中核として掲げてきました。
その理念に基づいて公明党を支え、与党として政策実現に寄与してきたわけですが、
近年は「政治とカネの問題」や「倫理軽視」の動きに対して、会員の中でも疑問の声が高まっていました。
- 「信仰に基づく政治参加」が“政権維持のための協力”に変質している
- 「清潔な政治」を掲げてきた学会の信頼が揺らぐ
- 「公明党は本来の理念を取り戻すべき」という内部の改革要求
このように、倫理性と現実政治の乖離が、今回の離脱を後押しした背景の一つといえます。
斉藤鉄夫代表の「信頼回復を最優先する」という発言も、学会内部の意向を反映しているとみられます。
3. 地方組織の分裂懸念と“自主投票”の可能性
創価学会は全国的に強固な組織ネットワークを有していますが、
地方レベルでは「自民候補を支援してきた歴史」が根強く残っています。
特に都市圏では、自民候補を支援してきた地方学会が多く、
今後は「自主投票」や「候補者ごとの判断」といった形で地域差が顕在化すると見られます。
これにより、公明党が一枚岩で選挙を戦うことは難しくなり、
短期的には比例票の減少や組織的分裂のリスクも指摘されています。
4. 公明党支持者の心理的転換
支持者の間では、今回の離脱を「信念を取り戻す第一歩」と捉える動きもあります。
- 「権力よりも信頼を選んだ」
- 「政権から離れても、理念を守る姿勢に共感する」
こうした声は、政治的行動において“信仰の一貫性”を重視する創価学会員の心理を象徴しています。
他方で、長年「与党=安定」という価値観のもと活動してきた世代にとっては、
この転換が「政治活動の再定義」を迫る大きな試練にもなっています。
5. 今後の支持構造と社会的影響
今後、公明党と創価学会は、次の3点を軸に関係を再構築していくと見られます。
- 政策連携の再定義
→ 「与党の一部」から「中立的政策提言者」へ。教育・福祉政策を中心に存在感を維持。 - 信頼回復の再構築
→ 「清潔な政治」を軸に再ブランディング。支持者との対話を重視。 - 地域社会での新しい政治参加の形
→ 政党支援から“政策支援”への移行。地域課題を基点にした協働型運動へ転換。
これにより、公明党は「宗教政党から市民政党へ」と変貌を遂げる可能性があります。
6. 社会へのメッセージ
創価学会関係者の中には、こう語る人もいます。
「権力のための政治ではなく、人を幸せにする政治に戻る。それが原点。」
この言葉が象徴するように、
自公連立の解消は、単なる政党再編ではなく、信仰・倫理・政治の三層構造が交差する“社会的再出発”です。
次章では、この動きを踏まえて、日本政治全体がどのような再編局面を迎えるのか――
第7章「今後の展望 〜新たな政治地図へ〜」で、政局・勢力図・選挙戦略の変化を包括的に分析します。
第七章 今後の展望 〜新たな政治地図へ〜

自公連立の終焉は、単なる政権の組み換えではありません。
それは、日本政治が“安定から競争へ”と構造転換する節目を意味します。
26年続いた「自民+公明=安定多数」という公式が崩れた今、政界は再び動き始めました。
1. 政権運営の新フェーズへ
高市早苗政権は、連立解消後、政治的孤立を避けるために迅速な対応を迫られています。
与党としての安定を失った今、次の3つの対応が焦点となります。
- 新連立の模索
→ 国民民主党や日本維新の会との「限定的政策連携」構想が浮上。 - 少数与党体制の維持
→ 重要法案を個別交渉で成立させる“法案ごと連携”モデルへ移行。 - 早期解散・信を問う戦略
→ 支持率低下を抑えるため、年内〜2026年前半に衆院解散の可能性。
つまり、自民党政権は「連立依存」から「機動的・多党協調型」への舵取りを余儀なくされています。
2. 公明党の新たな立ち位置
連立離脱後の公明党は、“中道独立路線”を強調しています。
斉藤鉄夫代表は会見で「何でも反対の野党にはならない」と明言し、政策ごとに協力を判断する方針を示しました。
これは、
- 与党との“是々非々”協力
- 政策中心の議論型政党
- 選挙よりも理念を優先する政治姿勢
への転換を意味します。
また、公明党は創価学会の支持を背景に、教育・福祉・平和といった分野で政策影響力を維持する戦略を取るとみられます。
3. 政界再編のシナリオ
自公分離は、他党にも波及し、政党勢力図が大きく変わる可能性を秘めています。
シナリオA:中道再編による「新連立構想」
- 自民+維新+国民民主による政策協定型の新与党ブロック
- 経済・防衛・憲法改正で協力し、社会保障・税制では調整型運営
シナリオB:リベラル勢力の再結集
- 立憲民主・れいわ・社民などが「反自民・反改憲」を軸に共闘強化
- 公明党が一部政策で協調する“部分連携”の可能性
シナリオC:政界分裂と多党化
- 自民党内部でも派閥再編・分裂の可能性
- 小党乱立による“令和型多党政治”への移行
このいずれの展開でも、日本政治は“二極構造”から“多極競争型”へと進化していくことが予想されます。
4. 政策軸の変化
自公体制下では、経済成長と安全保障が政策の二本柱でした。
しかし今後は、以下の3つの軸が政治議論の中心に移行します。
| 新時代の主要テーマ | 内容 | 主導勢力の例 |
|---|---|---|
| 政治倫理・資金透明化 | 政治資金規正法・企業献金禁止 | 公明・立憲・維新 |
| 社会的セーフティネット | 教育無償化・子育て支援強化 | 公明・国民・一部自民 |
| 経済構造改革 | 所得向上・企業税制見直し・労働改革 | 自民・維新・経済同友会系議員 |
このように、旧来の「安定運営型政治」から、“政策課題別連携”へのシフトが進むと考えられます。
5. 国民世論の変化
世論調査では、今回の連立解消に対し「評価する」と答えた割合が過半数を超えています。
特に若年層では、
- 「政党が理念で動くことを評価」
- 「政権交代の可能性が出た方が政治が活性化する」
という肯定的意見が目立ちます。
つまり、国民は「安定」よりも「透明性」と「競争原理」を重視し始めているのです。
これは、日本政治が成熟段階に入りつつあることを示す兆候といえます。
6. 政治の新時代へ
自公連立の26年間は、日本政治の“安定期”を象徴していました。
しかし、その安定の裏側では、政策停滞・倫理問題・世代交代の遅れといった課題が蓄積していました。
今後は、
- 政策ごとに政党が協働する柔軟な政治構造
- 国民の選択肢が多様化する政治環境
- 「理念・透明性・参加型政治」が求められる時代
が訪れます。
結び
自公連立の解消は、“終わり”ではなく“再出発”です。
政党・有権者・社会すべてが、再び「信頼できる政治とは何か」を問う局面に立たされています。
政治の安定は、もはや“数”ではなく“信頼”で決まる時代へ。
26年続いた同盟の幕が下り、日本は今、新たな政治地図を描き始めました。